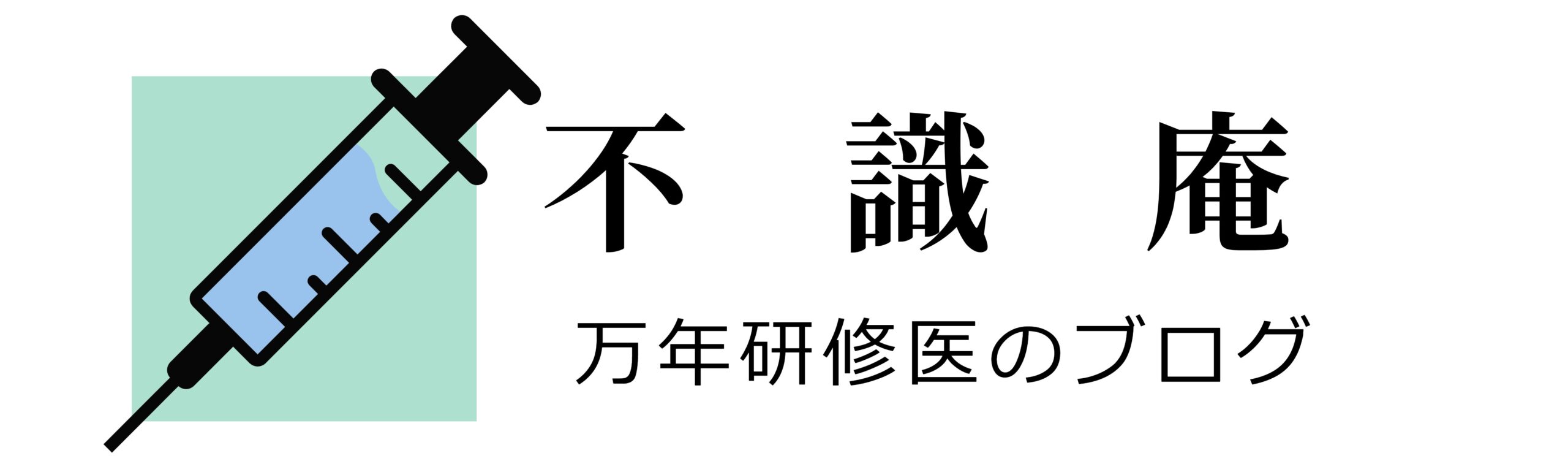更年期障害とは
定義
更年期は女性の加齢に伴う生殖期から非生殖期への移行期であり、わが国では閉経の前後5年の合計10年間と定義されています。閉経は月経が完全に停止して12か月連続していないことと定義されており、日本人女性の平均閉経年齢は50歳です。このため、ほとんどの人では45~55歳の期間が更年期に当たります。この更年期に現れる多種多様な症状の中で、器質的変化に起因しない症状を更年期症状と呼び、これらの症状の中で日常生活に支障をきたす病態を更年期障害と定義します。
疫学
わが国における更年期障害罹患患者数の正確な統計はありませんが、更年期に該当する40~60歳のうち、軽度の症状を含めれば60~80%が更年期症状を有すると考えられており、少なく見積もって約400万人が治療の対象となりうるという推計もあるようです。
病態
更年期障害の主な原因は、卵巣機能の低下によるエストロゲンをはじめとする女性ホルモンの「ゆらぎ」であると考えられています。一般的に、更年期障害はエストロゲンの低下が原因と認識されがちですが、実はこれは誤解です。
エストロゲンは閉経移行期から閉経後早期にかけて、大きく変動しながら低下していきます。この過程で、エストロゲンの値は上昇したり低下したりを繰り返します。このホルモンの急激な変動が更年期障害の症状を引き起こす要因となります。
したがって、更年期障害の診断において血清エストロゲン濃度を測定することは有用ではないことを覚えておきましょう。
また、更年期障害の発症には、このような内分泌変動や加齢といった身体的因子だけでなく、成育歴や性格などの心理的因子、家庭や職場における対人関係などの社会的因子が複合的に関与して発症に至ります。いわゆるBio-Psycho-Socialモデルがよく当てはまる疾患であり、心理・社会的背景に意識してアプローチを行うと、診療がスムーズです。

臨床症状
更年期症状はきわめて多彩ですが、非特異的身体症状、血管運動神経症状、精神症状の3要素に分解できることが多いです。
よく見られる非特異的身体症状として、「めまい」「頭痛」「疲れやすい」「嘔気」「手足のしびれ」「関節の痛み」「肩こり」などがあります。他にも消化器症状や狭心痛を訴えることもあり、更年期症状ではどのような身体症状であっても出現する可能性があります。
血管運動神経症状は、「顔が熱くなる、ほてる、のぼせる(いわゆる“ホットフラッシュ”)」「汗をかきやすい」という訴えが代表的です。夜間に症状が強い場合、「寝汗をかく」という訴えとなることがあり、結核や悪性リンパ腫との鑑別が必要になることがあります。
精神症状には「物事への関心が持てない」「何をしても楽しくない」「やる気が起きない」といったうつ症状、「いろいろなことが不安に感じる」「ちょっとしたことで緊張する」「気が動転しやすい」などの不安症状、「夜寝付けない」「熟睡感がない」などの不眠症状があります。このため、うつ病、双極性障害、全般性不安障害など、精神疾患との鑑別が重要となります。
診断
診断のポイント
実は、更年期障害の明確な診断基準は存在しません。これは更年期症状が非常に多彩でとらえどころがない上に、特異的な検査所見が存在しないことが要因です。考えてみれば仕方がないことなのですが、診断の羅針盤である診断基準がないというというのは、我々臨床家としては何とも困ったことです。
そこで、少しでも更年期障害の診断をスムーズにするために、①“更年期障害”を疑う、②自記的質問票を用い、症状を分析する、③鑑別すべき疾患を除外する、という3ステップを考えてみました。それぞれについて、詳しく解説していきます。
①“更年期障害”を疑う
診断の第一歩は、更年期障害を疑うことです。
更年期症状は「非特異的身体症状」、「血管運動神経症状」、「精神症状」の3要素から構成されることが多いと説明しましたが、この中で比較的疾患特異性が高いのは、ホットフラッシュをはじめとする「血管運動神経症状」です。そのため、この症状がある場合は、更年期障害を強く疑います。ただし、カルシウム拮抗薬の副作用や結核による夜間盗汗でも類似した症状が出るため、慎重な評価が必要です。
一方で、非特異的身体症状や精神症状は、血管運動神経症状と比較すると診断の決め手となりにくいlow yieldな症状であるため、個々の症状だけを見ていると更年期障害を想起できない可能性があります。そこで、ここで私が提唱したいのが、『更年期の女性患者に対し、「この人はなんだか不定愁訴が多いなぁ…」と感じた場合、更年期障害を疑う』というClinical Pearlです。
非特異的身体症状である「めまい」「頭痛」「疲れやすい」「嘔気」「手足のしびれ」「関節の痛み」「肩こり」に加え、精神症状を訴えるような患者さんを想像してみてください。おそらく、多くの方は“不定愁訴”とラベリングをし、少々診療が大変そうだと身構えるのではないでしょうか。この“不定愁訴”という言葉を用いることは、鑑別診断の観点からは有用性が低いだけでなく、患者さんに対する陰性感情につながる可能性もあるため、私は基本的には用いるべきではないと考えています。
ただ、発想を転換し、更年期の女性に「なんだか不定愁訴の多い人だなぁ…。」と感じた時に、更年期障害を鑑別に挙げる、という視点を持つことと、更年期障害の診断においては有用であるかもしれません。
②自記的質問票を用い、症状を分析する
更年期障害を疑ったら、次に症状の分析を行います。
ここで少し先の話をすると、次のステップ③では、更年期障害と診断する前に。鑑別すべき疾患の評価を行います。更年期障害の病型は多様であり、症状の種類や程度によって鑑別が必要な疾患も幅広くなるため、まず現在の症状を整理・分析することで、鑑別診断をスムーズに進めることができます。
症状の分析には、以下の日本産科婦人科学会、生殖・内分泌委員会が作成した自記的質問票を用いるとよいでしょう1)。

③鑑別すべき疾患を除外する
最後に、更年期障害と間違えやすい疾患の除外を行います。
先に述べた通り、多種多様な自覚症状の重症度に応じて鑑別すべき疾患は変化することに注意が必要です。例えば、「関節痛」や「指のこわばり」を訴える症例では関節リウマチが、「胸痛」を強く訴える症例では狭心症がそれぞれ鑑別に挙がります。ここでは、ステップ②で確認した自記的質問票による評価が有用であり、症状に応じて検査を勧めていきましょう。
更年期障害を疑った際、どのような場合でも必ず除外しておくべきなのが甲状腺機能異常です。甲状腺機能中毒症・亢進症、甲状腺機能低下症のいずれも更年期症状と似たような症状を呈しますし、中高年の女性に好発するという疫学も類似しています。このため、更年期障害の最大の鑑別疾患といっても過言ではなく、最初の血液検査でルーチンで甲状腺機能を評価しておくことが望ましいです。
関節症状が強い場合には関節リウマチの可能性を考えますが、特にリウマトイド因子や抗CCP抗体が陰性となる血清反応陰性関節リウマチは否定が難しいため、慎重に評価する必要があります。よって、関節症状が目立つ場合、可能であれば一度膠原病内科医による評価を依頼するとよいと思います。
また、精神症状が強い場合は、うつ病などの鑑別が必要です。もちろん、更年期障害と精神疾患が併存している可能性もあるため、判断が難しい場合は精神科・心療内科へのコンサルトも検討しましょう。うつ症状が強い場合、必ず希死念慮がないかは確認すべきです。希死念慮がある場合には、緊急での対応が必要となります。
治療
更年期障害の治療目標は、更年期症状を軽減し、患者のQOLを向上させることにあります。薬物療法だけで改善させることは難しく、診療を継続していく中で患者さんが身体的、心理的、社会的状況を受容できるように支援していくことが重要です。その上で、更年期障害の治療を心理療法と薬物療法の2つにわけて解説をしていこうと思います。
心理療法
まずは受容と共感を持って患者さんの訴えを傾聴し、背景にある心理・社会的要因を探ることが重要です。当然ながら、「不定愁訴が多くて面倒だ」といった偏見を持ち、粗雑な対応をするのはNGです。
更年期にあたる50歳前後は、管理職への昇進による職場環境の変化、子供の巣立ちによる「空の巣症候群」、夫婦関係の再構築など、社会的ストレスイベントが多発しやすい時期です。こうした年齢特有のライフイベントを念頭に置いて問診を行うと、診療がよりスムーズに進みます。
認知行動療法をはじめとする心理療法の有効性は明らかになっています。しかし、本格的な心理療法を実施するには専門的な訓練が必要であり、時間と労力の面からも日常診療での実践は難しいのが現実です。とはいえ、患者さんの訴えに耳を傾け、心理・社会的要因を丁寧に探ること自体が、簡易的な心理療法として十分に効果をもたらします。診療を重ねる中で患者さん自身に気づきが生まれ、それが行動変容につながり、結果として症状が軽減する――これはまさに認知行動療法のプロセスと通じるものです。
薬物療法
薬物療法には、①ホルモン補充療法(hormone replacement therary:HRT)、②漢方、③向精神薬という、3つの選択肢があります。
①ホルモン補充療法(hormone replacement therary:HRT)
近年、HRTは深部静脈血栓症や乳がん・子宮体がんなど、副作用が強調され忌避される傾向がありますが、血管運動神経症状に対しては最も有効な治療法です。また、気を付けて運用すれば、副作用を最小限に安全に使用することも可能です。
子宮が存在する女性にはエストロゲンと黄体ホルモンを併用し、子宮摘出後の女性にはエストロゲン単剤を用います。これは、子宮の存在する女性にエストロゲンのみを投与すると、子宮内膜増殖症のリスクが著明に増大するためです。
また、エストロゲンは経皮投与を行うことで、深部静脈血栓症のリスクが増大しないこともわかっており、最近は貼付製剤が普及してきているようです。
ただ、プライマリケア医がHRTを行うのはなかなかハードルが高い印象です。実施するとしても、専門家のバックアップを受けることが望ましいでしょう。
②漢方薬
更年期障害において、漢方薬は一定の有効性が期待できます。よく用いられるのが、「婦人科三大処方」とも呼称される加味逍遙散、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸の3剤です。
更年期障害は気血水の三要素で考えると、血の異常である瘀血があることが多いです。そこに虚実の評価、血虚・気逆の有無など、他の要素を検討して薬剤を選択していきます。
ざっくりとですが、以下に3剤の使い分けをまとめました。

これを見ますと、典型的な更年期障害には加味逍遙散がよく効いてくれそうですね。もちろん、症状によっては他の漢方薬を用いることもありますが、まずはこの3剤を使いこなせるようになりましょう。
③向精神薬
うつ症状、不安、不眠などの精神症状には、向精神薬の使用を検討します。ただ、精神症状があまりにも前景に立っている場合は、やはり精神科・心療内科へのコンサルトが無難でしょう。
うつ症状にはSSRIやSNRIが有用であり、さらに血管運動神経症状を軽減する可能性も示唆されています。不安が強い場合には、ベンゾジアゼピン系薬を頓用で処方し、不眠症状に対しては睡眠薬を併用するとよいでしょう。ただし、ふらつきなどの副作用や、依存性には注意して運用するべきです。
まとめ
以上、三種類の薬物治療について概説してきました。個人的な意見ですが、プライマリケアのセッティングでは、薬物治療としては漢方薬を使用するのがよいと考えます。やはりHRTや向精神薬を非専門医が処方することはハードルが高く、できれば専門医による介入が望ましいでしょう。一方、漢方薬は最低限の東洋医学的なアセスメントさえできていれば大きな間違いはなく、プライマリケア医でも気軽に処方できます(もちろん、漢方薬にも間質性肺炎や肝障害といった有害事象はある点は医師は把握しておくべきですし、患者さんにも説明しておく必要がありますが)。繰り返しにはなりますが、更年期障害に適した漢方薬として、まずは加味逍遙散、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸の3剤を覚えるようにしましょう。最初はとっつきにくいかもしれませんが、漢方薬が手札に加わると診療の幅が広がります。皆さんも、是非この機会に漢方薬を使ってみてはいかがでしょうか。
なお、余談ですが、加味逍遙散に含まれている生薬であるサンシシにより、腸間膜静脈硬化症という慢性虚血性大腸病変が生じることがあります3)。症状としては、慢性的な腹痛、下痢、便秘、血便といった消化器症状が出現します。5年以上の長期内服により発症リスクが高まるとされており、加味逍遙散を長期に継続する場合には注意が必要です。なお、その他に生薬としてサンシシを含む漢方薬には、黄連解毒湯、辛夷清肺湯、防風通聖散などがあります。
参考
1)産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2023 日本産婦人科学会、日本産婦人科医会
2)今日の臨床サポート
3)漢方薬による腸間膜静脈硬化症 https://www.nikkankyo.org/seihin/pdf/m_phlebosclerosis.pdf
4)UpToDate