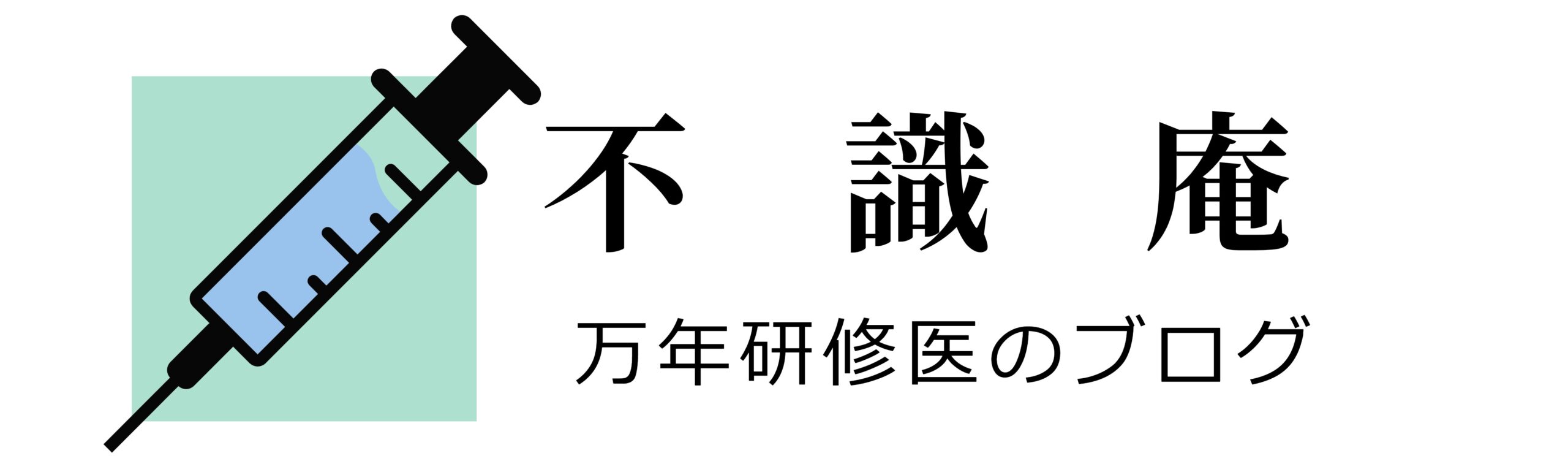定義・病態
注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder:ADHD)とは、発達障害の一種であり、“複数の状況で認められる発達水準に不相応な多動性-衝動性、不注意によって特徴づけられる疾患”です。多動性-衝動性と不注意は混在することもあれば、どちらか一方が優位に存在することもあります。
ADHDは従来は小児の疾患として扱われてきましたが、その後成人まで持続する例が少なくないことが認識され、成人期まで持続しうる発達障害として認識されるようになってきています。ADHDによって成人期に職務などの日常生活に支障を来したり、うつ病などの精神疾患が誘発・増悪されることも少なくないため、プライマリケア医も概要を押さえておくべき疾患であると考えます。
ADHDの病態は解明されていませんが、注意機能領域である前頭皮質と、関連する神経回路の機能低下が仮説として有力です。また、これらの神経回路の神経伝達物質であるドパミン、ノルアドレナリンの活性低下も要因の一つと考えられています。このような病態仮説を踏まえ、ADHDの治療薬としてドパミン、ノルアドレナリンの濃度を増加させる薬剤が使用されています。
疫学
〇有病率・男女比
ADHDの有病率は年齢や地域によって異なりますが、小児・成人のそれぞれで以下の通りと推計されています。
小児:9~15%
成人:世界全体で2.6%(先進国では4.2%、発展途上国では1.9%)
女性よりも男性に多くみられることも特徴です。多動性・衝動性優位の ADHDでは男女比4:1、不注意優位では男女比2:1となっています。
〇併存しやすい疾患
ADHDでは併存しやすい疾患が多く、診断した際には他の疾患の合併がないかもチェックすることが望ましいです。具体的な疾患を列挙しますと、小児と成人で以下のようになっています。
小児:反抗挑戦性障害、素行障害、うつ病、学習障害、発達性協調運動障害、自閉症スペクトラム症、睡眠障害
成人:うつ病などの気分障害、不安障害、あらゆる物質使用障害
症状
小児期
ADHDの中核症状は、多動性-衝動性と不注意という2つのカテゴリーに分類されます。
〇多動性-衝動性
多動性-衝動性行動は、幼児期にほぼ同時に現れます。通常は4歳になるまでに出現し、その後3~4年間で増悪して7~8歳で症状のピークを迎えます。以降、多動性は徐々に改善していき、思春期にはほとんど目立たなくなります。対照的に、衝動性は生涯にわたって改善せず持続します。このため、思春期には衝動性をきっかけとし、薬物乱用や危険な性行動といった、不適切な行動をとってしまうこともあります。
多動性-衝動性を表す具体的なエピソードとして、以下のようなものが挙げられます。
・過度の落ち着きのなさ(手や足をたたく、座席で身をよじる)
・座ったまま待つことができない
・不適切に走り回ったり、よじ登ったりする
・楽器をやたらとうるさく演奏してしまう
・私語が多くおしゃべりである
・順番を待てない
・思ったことをすぐに口にがしてしまう
・他人の行動を妨害する
・まっすぐ人についていくことが難しく、常に落ち着きなく動き回っているようにみえる
〇不注意
不注意の症状は8~9歳以降に顕在化し、衝動性と同様に生涯持続します。
具体的には、以下のようなエピソードを呈します。
・細部に注意を払わない、不注意なミスをする
・遊び、学校、家庭での活動で注意を維持できない
・直接話しかけられても聞いていないように見える
・宿題、家事をやり遂げることができない
・タスク管理ができない
・持ち物の生理ができない
・長時間集中が必要な作業を避ける
・よくものをなくす
・無関係な刺激に簡単に気を取られる
・日常的な活動をやり忘れる
小児期の場合、親、教師、保育者などが、養育の困難さに気が付き、ADHDの診断に至ることが多いです。本人から直接症状の訴えがあることは少ないのですが、ADHDの症状によって友人とのコミュニケーションに齟齬を生じ、社会的に孤立し苦痛を感じていることが少なくありません。
成人期
成人期の場合、以下のように小児期とはADHDのプレゼンテーションが異なります。
多動性:ほとんど目立たない
衝動性:身体行動ではなく、言語行動に現れる傾向がある
不注意:小児期より顕著になる
〇多動性-衝動性
成人期では多動性はあまり目立ちませんが、他人から落ち着きがないとみなされやすい傾向があります。
一方、衝動性は具体的な行動というよりも、思ったことをすぐ口に出してしまうような言語行動として表現されることが多いです。また、他者との関係を断ち切る、すぐに仕事を辞めるといった行動をとってしまうこともあります。
〇不注意
不注意は成人期のADHDの症状の中でも、最も前景に立つものです。具体的には、以下のような問題を引き起こします。
・仕事に対し、長時間の集中ができない
・活動の計画が立てられず、行き当たりばったりに行動してしまう
・タスクの優先順位をつけられない
・タスクをやり遂げられない
・ものをよく紛失する
・待ち合わせや締め切りなど、時間が守れない
成人期の場合も、患者さん本人が衝動性や不注意を主訴に医療機関を受診することは少なく、むしろADHDによって誘発された適応障害やうつ病など、他疾患が診断のきっかけとなることが多いです。成人期の場合、不注意症状によって職場でトラブルを生じやすく、場合によっては失業に繋がる可能性もあり得ます。受診の理由が何であれ、社会生活に支障をきたしているような場合、成人のADHDの可能性を一度は想起するのがよいと思います。
また、ADHDの患者さんは労働災害による外傷、交通事故を起こすリスクが高いことも知っておきましょう。
診断
ここでは、ADHDの診断について確認していきます。
早速ですが、以下にDSM-5の診断基準をお示しします。

ちょっと複雑ですが、簡単にまとめますと、
・不注意・多動性-衝動性による症状があり、
・それらが12歳以前から存在し、
・特定の環境だけではなく、複数の環境で再現性をもって出現し、
・日常生活に支障をきたしており、
・他の疾患で説明がつかない
という場合にADHDの診断になる、ということになります。
基本的にはこの基準を使用して診断していくことになるのですが、これだけでは具体的にどのように問診すればよいのか、なかなかイメージがつかないですよね。ですので、ここでは成人期のADHDの診断に有用なツールについて、いくつか紹介したいと思います(なお、小児については専門性が高そうなので断念しました…)。
①ASRS(Adult ADHD Self-Report Scale)
・世界的に広く使用されている自己記入式スクリーニングツールです。
・Part AとPart Bで構成されています
・Part A(6項目)が特にスクリーニングに有効で、4項目以上が基準を超える場合、ADHDの可能性が高いとされます。
・日本語版もあり、簡便に使用できます。
・精度も比較的高く、初診でのトリアージや主観的訴えとのギャップを見るのにも有用です
②DIVA-5(Diagnostic Interview for ADHD in Adults)
・DSM-5に準拠した、半構造化面接形式のツールです。
・小児期と現在の症状の両方を評価することができます。
・本人の主観+家族や親からの情報を総合的に確認しながら進めるスタイル。
・日本語版も利用可能(DIVA-J)
・1時間程度かかる検査ですが、診断確定のための面接ツールとして非常に信頼性が高いです。
③CAARS(Conners’ Adult ADHD Rating Scales)
・ADHD症状を多角的に評価するツールで、自己評価版と他者評価版があります。
・注意欠如、衝動性、情緒的側面など、症状を細かく可視化できます。
・薬物療法の効果判定などにも有用。
④WAIS-IV(知能検査)や実行機能検査(TMT、WCSTなど)
・ADHDは認知機能(ワーキングメモリ、処理速度など)の偏りを伴うことがあるため、WAIS-IVのプロファイル分析も診断補助として有効です。
・特に「処理速度<ワーキングメモリ」「語彙>符号」などのパターンが参考になることがあります。
実際には、“ASRSでスクリーニングを行い、陽性であればDSM-5に基づく症状の聴取、面談(DIVA-5など)をして診断をつける”というフローになると思われます。ただ、プライマリケア医はASRSによるスクリーニングを行うことができれば十分だと考えます。スクリーニング陽性例は、専門医に紹介して確定診断を含めた評価を依頼するのがよいでしょう。
治療
治療は専門医に依頼するのが望ましいと考えますが、どのようなものか全体像について触れておきたいと思います。
非薬物療法
ADHDの治療において最も重要なのが、環境調整と心理社会的治療などの非薬物療法です。ADHDの患者さんは、症状によって社会生活に支障をきたし、苦しんでいることが多いです。特に成人期ADHDでは、本人の生活・仕事・人間関係に根ざした支援が治療効果を大きく左右します。以下に代表的な非薬物療法をまとめます。
①環境調整
・ADHD特有の「注意の散逸」や「忘れやすさ」などを軽減するための、生活・仕事の構造化が中心になります。
・具体例:
①タスクリスト・スケジュール帳・スマホのリマインダー活用
②デスク周りの整理整頓、刺激の少ない作業環境
③大きな仕事を小さく分割し、1つずつ達成
④親やパートナー、職場の上司との情報共有(配慮事項の周知)
→ 「見通しが立つ」「混乱しない」環境に整えることがポイントとなります。
②認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)
・ADHDに伴う自己否定感や失敗体験による不安・抑うつなどの二次的問題へのアプローチとして有効です。
・課題管理スキルや思考のクセを見直す訓練にもなります。
・ 内容例:
①タイムマネジメントの練習
②「すぐ気が散る」などの自動思考への対応法
③実行機能を補う戦略の習得(行動計画、優先順位づけなど)
③コーチング
・ADHD当事者に特化した日常生活のサポート、コーチングを行います。
・一対一で、スケジュール管理や行動変容を継続的に支援する形式です。
→精神科医療よりもカジュアルなスタイルで利用されることも多く、海外では盛んであるようです。
④家族・職場への支援と教育(Psychoeducation)
・本人だけでなく、家族や職場にADHDの特性を理解してもらうことも治療の一部です。
・ 対応内容:
①ADHDは「怠け」ではなく「神経発達症」であることの説明
②配慮が必要な場面の共有
③叱責や否定でなく、建設的なコミュニケーションの促進
⑤就労・学業支援
・職場や学校での合理的配慮の相談・実行を調整します。
・例:静かな作業スペース、スケジュールの明確化、説明の工夫など。
→就労支援機関(就労移行支援など)や、発達障害者支援センターとの連携が有効。
むろん、これらは医師のみで行うことは困難ですので、多職種、両親、職場、学校など、多方面でコミュニケーションをとりながら勧めていくことが重要です。
薬物療法
本邦では、非薬物療法に対し十分な反応がみられない患者さんに対して薬物療法を実施します。
薬剤には中枢刺激薬と非中枢刺激薬にわけられ、本邦では次のような選択肢があります。
・中枢刺激薬:リスデキサンフェタミン(ビバンセ®)、メチルフェニデート(コンサータ®)
・非中枢刺激薬:アトモキセチン(ストラテラ®)、グアンファシン(インチュニブ®)
中枢刺激薬は依存リスクがあるため、処方医の登録制がある点に注意が必要です。
まずはメチルフェニデート、アトモキセチン、グアンファシンのいずれかを用い、効果がみられない場合にリスデキサンフェタミン、あるいは併用療法を行います。
参考
1)UpToDate
2)今日の臨床サポート