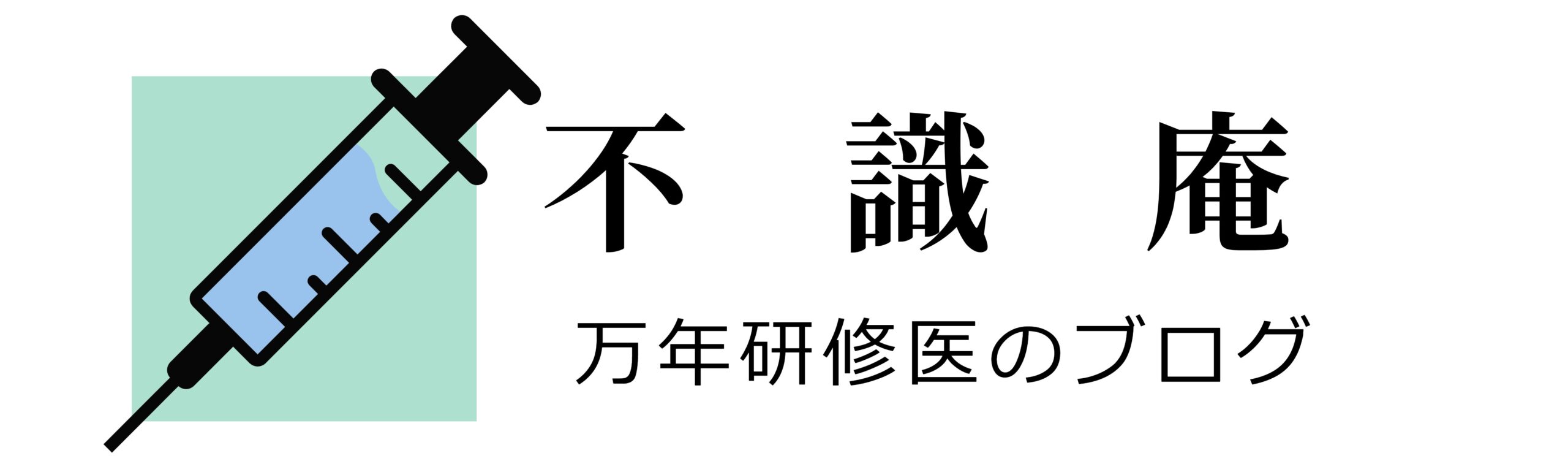緊張病とは
緊張病(Catatonia)とは、身体的には異常がないにもかかわらず、正常に動くことができなくなる症候群です。主に精神疾患の一症候としてみられますが、身体疾患が原因となることもあることが分かっています。
先日、緊張病を疑う患者さんを診療する機会がありました。これを機に、緊張病について整理してみたいと思います。
臨床的特徴
症状
緊張病の症状は、以下のように運動面の異常と行動・言語面の異常に分類されます。
①運動面の異常
・昏迷(catatonic stupor)
動作や言動が極端に少なくなり、ほとんど反応がなくなる状態。
・カタレプシー(強硬症・ろう人形様現象)
他者が患者の四肢や体幹をある姿勢にすると、その姿勢を長時間にわたって維持し続ける症状。
・ワクシー・フレキシビリティ(蝋屈症)
カタレプシーと関連し、身体を動かそうとすると抵抗があるものの、ゆっくり動かすと関節が「蝋(ろう)」のように曲がる現象。
・興奮(catatonic excitement)
理由なく突然に激しく動き回ったり、大声を出したり、暴力的になる。
②行動・言語面の異常
・無言症(mutism)
声を発する能力があるにもかかわらず、全く話さない、もしくはごくわずかしか話さない状態。
・拒絶症(negativism)
指示に反する行動をとったり、全く応じない状態。
・反響言語(エコラリア:echolalia)
他者の言った言葉をそのまま反復する。
・反響動作(エコプラクシー:echopraxia)
他者がとった行動をそのまま真似して繰り返す。
サブタイプ
緊張病は、経過や症状によっていくつかのサブタイプに分類されます。精神医学ではこのような分類は正式には認められていませんが、臨床像を把握するために有用です。ここでは、遅滞型、興奮型、悪性という3つのサブタイプを紹介します。
①遅滞型緊張病
緊張病の中で最も多い病型です。無言症、拒絶症、混迷、カタレプシーを特徴とし、体動が極端に少なくなります。外界刺激への反応性が低下し、発語や自発運動が減少しますが、軽症の場合はコミュニケーションが取れることもあるようです。重篤な症例では経口摂取が困難となり、混迷、失禁を呈することもあります。
②興奮型緊張病
興奮型は遅滞型について多い病型であり、上下肢の無目的な運動(多動)、不穏・焦燥、情動行動が目立ちます。全体的に体動が多いため、私たちの中での典型的な緊張病とは解離があるかもしれません。重篤な場合は自傷行為や他害に繋がることもあります。
③悪性緊張病
悪性緊張病は致死性緊張病とも呼称され、発熱、自律神経症状(高血圧、頻脈、頻呼吸、発汗)、せん妄、固縮を特徴とします。典型的には数日以内に悪化する、急速進行性の経過を辿ります。白血球増多やクレアチンキナーゼの上昇を伴うことがあり、悪性症候群に類似した病像を示します。
病態と基礎疾患
病態
緊張病の病態生理はよくわかっていませんが、基底核と皮質および視床を結ぶ経路が関与しているという仮説が提唱されています。実際、統合失調症患者においては、病理学的に基底核と視床の変化が認められているそうです。
基礎疾患
緊張病そのものは一つの疾患というよりも、ある基礎疾患によって生じる一つの症候群として解釈されます。双極性障害、うつ病、統合失調症に代表される精神病、せん妄など、精神疾患が原因となることが多いです。
その一方で、緊張病の約20%は身体疾患が原因であるとされており、ヘルペス脳炎や抗NDMA受容体脳炎などの脳炎、電解質異常や橋本脳症などによる脳症、脳腫瘍、認知症など、多彩な疾患が基礎疾患として報告されています1)。特に、抗NMDA受容体抗脳炎では約40%に緊張病を伴うようです2)。
また、抗精神病薬や抗てんかん薬、ステロイドなど、基礎疾患に対する治療が緊張病の誘因・増悪因子となることもあります。
評価
評価における注意点
緊張病はスペクトラムの広い症候群であり、診断の見落としが意外と多くなりがちです。
例えば、遅滞型の緊張病であれば診断は比較的容易ですが、無言症、カタレプシー、無動といった典型的な症状が欠如している場合、特に興奮型緊張病では鑑別から漏れやすい傾向があります。
さらに、基礎疾患そのものの症状と、緊張病の症状に連続性があることも診断を難しくします。例えば、うつ病では無気力、運動量の低下、食思不振といった症状がよく見られますが、これらは緊張病の症状としても認められます。また、双極性障害がある場合、活動量や衝動性の増加が双極性障害によるものなのか、それとも興奮型緊張病の症状なのかを区別することは難しい場合があります。
見逃さないコツとして、冒頭で紹介した緊張病の主症状を把握し、一つでも該当する患者さんを診療した際、「これってもしかして緊張病かな?」と疑うよう心掛けるとよいでしょう。
診断
DSM-5の緊張病の診断基準は、「混迷、カタレプシー、蝋屈症、無言症、拒絶症、姿勢保持、わざとらしさ、常同症、外的刺激の影響によらない興奮、しかめ面、反響言語、反響動作のうち、3つ以上が優勢であるもの」と定義されています。緊張病を疑った場合、この診断基準を基に評価を行うとよいと思います。
また、緊張病の診断にはロラゼパムチャレンジが有効とされています。ロラゼパムチャレンジでは、ロラゼパム 1~2mgを静脈内投与を行い、反応性を確認します。5~10分後に症状の改善が見られた場合、緊張病である可能性が高いです。代替法として、ロラゼパム2mg内服も選択肢となります。
緊張病の鑑別疾患としては、以下のようなものがあります。
・悪性症候群
・セロトニン症候群
・無動性緘黙症(運動前野、運動前野の損傷)
・心因性無言症
・非痙攣性てんかん重責状態
・パーキンソン病を含めたパーキンソン症候群
・脳卒中
・せん妄
・認知症
これらの多くは病歴や身体診察、頭部画像検査で鑑別が可能ですが、一部の疾患、具体的には非痙攣性てんかん重責状態や急性発症のパーキンソン症候群の場合は緊張病との区別が難しいことがあり、注意が必要です。加えて、非痙攣性てんかん重責状態はロラゼパムに反応してしまうことも頭に入れておきましょう。
まとめますと、DSM-5による診断基準を満たし、ロラゼパムチャレンジが陽性であり、かつ鑑別疾患がいずれも否定的であれば、緊張病と診断して差し支えないです。
緊張病の診断となった場合、可能であれば精神科医と連携して診療に当たるのがよいでしょう。また、悪性緊張病は致死的となりうるため、すぐに精神科医にコンサルトを行い、場合によっては転院搬送も考えるべきです。
基礎疾患の検索
緊張病の基礎疾患は精神疾患から身体疾患まで幅広いため、過不足なく網羅的に検索するのはなかなか難易度が高いです。単純明快なフローなどはなく、泥臭くアプローチするしかなさそうです。以下、病歴聴取や身体診察、検査に関し、ポイントをまとめます。
①病歴聴取
・既往歴・家族歴:統合失調症や双極性障害、うつ病などの精神疾患の既往や家族歴、自己免疫疾患や代謝異常、神経疾患などの身体疾患がないか確認する。
・薬剤歴、物質使用歴:抗精神病薬、抗うつ薬、ステロイド、向精神薬、違法薬物などの使用状況を把握する。特に抗精神病薬を服用している場合、悪性症候群や薬剤性パーキンソニズムとの鑑別が必要。
・症状の経過:いつ頃から、どのような状況で症状(運動停止、興奮、反響言語・反響動作、拒絶症など)が始まったかを確認する。その前にうつ病や双極性障害、統合失調症を疑う症状がなかったかも聴取するとよい。
②身体診察・精神状態評価
・全身状態の把握:発熱、血圧、脈拍、呼吸状態、脱水の有無、栄養状態などをチェックする。血圧高値や頻呼吸。頻脈など、自律神経異常がある場合は、悪性緊張病に加え、鑑別である悪性症候群やセロトニン症候群の可能性も考える。
・神経学的所見:意識レベルや神経学的な異常(麻痺や感覚異常、硬膜刺激症状など)がないかを確認する。パーキンソン症候群を鑑別するため、錐体外路徴候がないかはよくチェックしておく。
・精神状態の評価:緊張病の典型症状(カタレプシー、ワクシー・フレキシビリティ、昏迷、反響言語・反響動作、無言症、拒絶症など)の有無と程度を把握する。
③基本的な検査
・血液検査
一般血液検査(CBC):貧血、白血球数や炎症反応をチェックする。
生化学検査:電解質(Na, K, Clなど)、腎機能(BUN, クレアチニン)、肝機能(AST, ALT, γ-GTP など)、血糖値、カルシウム・マグネシウムなどを評価し、代謝異常や臓器障害の有無を確認する。
甲状腺機能(TSH, FT3, FT4):甲状腺機能低下症や亢進症による精神症状を鑑別。
炎症反応・感染関連(CRP、血沈など):感染症や自己免疫疾患の可能性を検討。
クレアチンキナーゼ:特に悪性症候群の疑いがある場合には必須。
・尿検査による薬物スクリーニング:薬物乱用や毒性による影響を除外するため、必要に応じて確認する。
・画像検査:頭部CT / MRI:脳梗塞、腫瘍、炎症性病変、萎縮、その他の器質的病変の有無を評価する。
・脳波検査(EEG):てんかん活動や代謝性脳症などが疑われる場合に実施する
④必要に応じた追加検査
・髄液検査(腰椎穿刺):緊張病の背景に脳炎があることは少なくないため、疑わしい場合には躊躇せず行うべきである。
・自己抗体検査:抗NMDA受容体脳炎など自己免疫性脳炎を疑う場合、血清・髄液検査でNMDA受容体抗体などの検索を行う。
・副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど):ステロイドの過剰・不足による精神症状の可能性を検討。
治療
緊張病の治療の基本
緊張病治療の第一選択は、ベンゾジアゼピンか電気けいれん療法(ETC)です。悪性緊張病の場合は迅速にETCを行う必要があるため、対応ができない場合は高次医療機関への搬送も検討します。一方、非悪性緊張症の場合、病型が遅滞型か興奮型かに関わらず、ベンゾジアゼピンによる治療を行います。
ベンゾジアゼピン(ロラゼパム)の使い方
ベンゾジアゼピンの投与により、60-80%の患者に反応があるとされています3)。治療においても、ロラゼパムが使用されることが多いようです。
通常、3~6mg/日を分3投与で開始されます。その後、患者の反応・副作用をみて、1-2日ごとに3mg/日ずつ増量していきます。ほとんどの場合、6~21mg/日の用量で効果がみられ、4-10日程度でほぼ症状が消失します。内服が困難である場合には静注製剤を使用してもよいです。
ロラゼパムへの反応が乏しい場合、ETCが選択肢となるため、専門医へのコンサルトが必須となります。
抗精神病薬(ドパミン遮断薬)の中止
すべての抗精神病薬は緊張病を誘発・悪化させるため、投与を中止することが望ましいです。ただし、抗精神病薬の中止が悪性症候群を誘発する可能性もあり、一律に中止することは危険です。できれば精神科医と連携し判断するのがよいでしょう。
参考
1)J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2012 Spring;24(2):198-207.
2)UpToDate:Catatonia in adults: Epidemiology, clinical features, assessment, and diagnosis
3)UpToDate:Catatonia: Treatment and prognosis