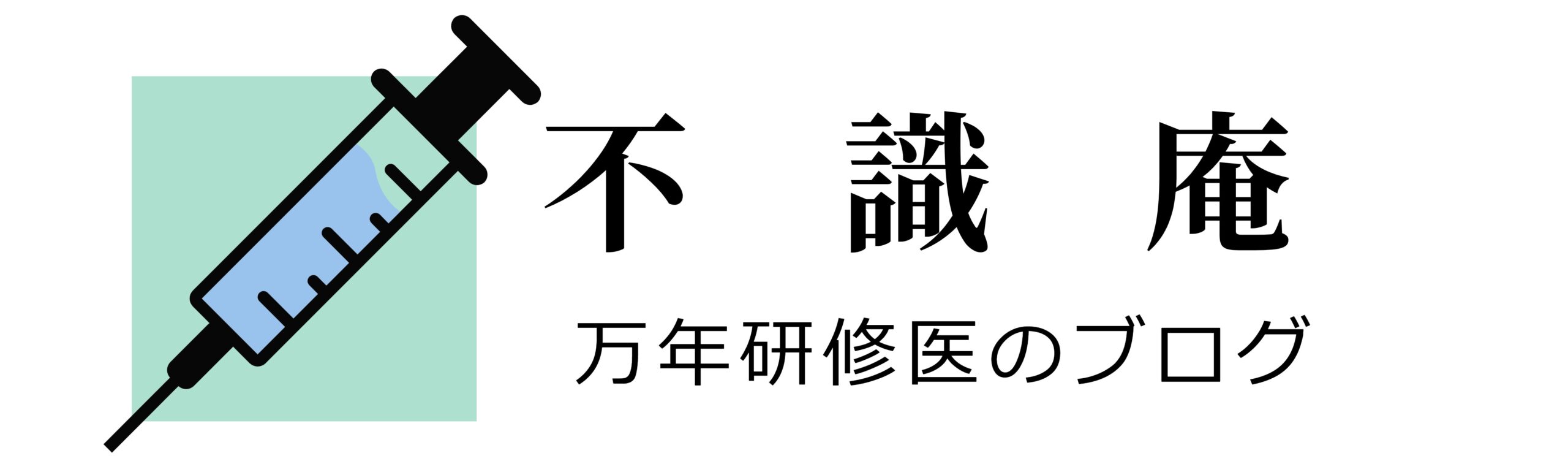医療現場では、原因がはっきりしない身体症状に日々直面します。検査で異常がなく、器質的疾患も見当たらない。けれども、患者さんの訴えは強く、日常生活への影響も小さくありません。
こうしたケースでよく登場するのが、「MUS(医学的に説明のつかない症状)」「FSS(機能性身体症候群)」「身体表現性障害」「心身症」などの用語です。最近では、DSM-5に新たに加わった「身体症状症(Somatic Symptom Disorder)」という診断名も知られるようになりました。
しかし、これらの用語は互いに重なりも多く、現場での使い分けに迷うことも少なくありません。「MUSとFSSはどう違うの?」「心身症と身体症状症は同じ意味?」──こんな疑問を持ったことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、まずそれぞれの用語の定義や背景を整理し、「身体症状症」という診断名がどういった概念の上に成り立っているのかを解説していきます。
用語の整理:似て非なる概念を区別しよう
まずは用語の整理をしていきましょう。ここでは、以下の5つの用語について整理していきます。
①MUS(Medically Unexplained Symptoms)
②FSS(Functional Somatic Syndromes)
③心身症(Psychosomatic Disorders)
④身体表現性障害(Somatoform Disorders)
⑤身体症状症(Somatic Symptom Disorder)
①MUS(Medically Unexplained Symptoms)
MUSとは、「医学的に説明困難な身体症状」と直訳され、「何らかの身体疾患が存在するかと思わせる症状が認められるが、適切な診察や検査を行ってもその原因となる疾患が見出せない病像」とされています。器質的疾患で説明がつかない身体症状全般がMUSに該当するため、今回紹介する用語の中でも最も広範な概念であるといえます。
注意すべき点として、診断が下っていない身体疾患や精神疾患も含まれており、医師の診断能力によってMUSと診断される症例が増えてしまうことは覚えておきましょう。自信をもって“医学的に説明困難”というところまで言える所まで、他疾患を除外した上で使用すべき用語ということですね。
また、よく使われる「不定愁訴」や「非器質的疾患」という用語がありますが、これらも基本的にはMUSと同じスペクトラムの意味合いだと考えて頂いて差し支えないです。
②FSS(Functional Somatic Syndromes)
FSSは「機能性身体症候群」と訳され、「症状の訴えや傷つき、障害の程度が、確認できる組織障害の程度に比して大きいという特徴をもつ症候群」と定義されています。代表的な疾患としては、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群、緊張性頭痛、月経前症候群、線維筋痛症、咽喉頭異常感症などが該当します。単に“機能性疾患”と呼称されることもあります。
機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群を例にとると、まずは腹部超音波検査、消化管内視鏡検査などの検査を行い、器質的な異常を認めないことを前提に診断を行います。
それぞれ独立した疾患単位として認知されることが多いですが、それぞれがオーバーラップすることも少なくないため、全体として大きな症候群単位でとらえておくのがよいでしょう。
③心身症(Psychosomatic Disorders)
心身症とは、「身体疾患の中で、その発症や経過に心理社会的因子が密接に関与し、器質的ないし機能的障害が認められる病態」と定義されます。ただし、うつ病など他の精神障害に伴う身体症状は除外する必要があります。
心身症は、さらに器質的心身症と機能的心身症に分類されます。前者には胃潰瘍、高血圧症、喘息などが含まれ、後者には過敏性腸症候群、機能性ディスペプシア、線維筋痛症が含まれます。お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、包含されている疾患群をみると、先ほど紹介したFSSと機能的心身症はかなりオーバーラップしている概念であることがわかりますね。
また、“心身症=精神疾患”というのはよくある誤解であり、注意しましょう。定義にもある通り、心身症は身体疾患であり、必ず身体の病気である必要があります。よって、精神疾患の分類としてよく用いられるDSM-5にも心身症の項目は存在していません。
加えて、“心身症=精神疾患の身体症状”ではないこともおさえておきましょう。定義にもある通り、心身症とするには他の精神疾患による身体症状を否定することが必要です。一方で、精神疾患と各種の心身症が併存することは珍しくなく、精神疾患と心身症がお互いの経過に影響を与えうる関係であることは理解しておきましょう。
カルテ上の記載ですが、もし喘息があり、心身症の要素がある場合は、
#1.喘息(心身症)
と記載するのがよいでしょう。
あくまで器質的疾患ベースの概念であるため、
#1.喘息
#2.心身症
という記載の仕方は好ましくありません。
④身体表現性障害(Somatoform Disorders)
DSM-4まで使用されていた診断カテゴリーで、「医学的に説明できない身体症状」を診断の中心としていました。
ただ、
・「医学的に説明できない」という証明が難しい
・「説明できない=心因性」というアプローチであるため、患者さんの訴える症状の存在を軽視している
といった問題、批判があり、DSM-5で身体症状症という新しい診断カテゴリーを導入し、症状そのものではなく、それに対する心理的・行動的反応の強さを診断の焦点としました。
よって、現在はこの診断名を用いることは正しくないのですが、本邦では本診断名が保険診療で今も用いられている点に注意が必要です。
⑤身体症状症(Somatic Symptom Disorder)
前述の通り、DSM-5で新設された診断名です。最大の特徴は、「身体症状が医学的に説明可能かどうか」に関係なく、患者さんに症状による過度な不安、苦痛、行動変化が起こっていないかを重要視している点です。身体症状が実在し、苦痛が本物であることを前提にマネジメントを行っていきます。詳しい診断基準などは後述します。
ちょっと整理が難しいと思いますので、上記のような概念を図にまとめますと、以下のような関係性となります。

身体症状症とは?
さて、ここからは身体症状症に関し、深堀していきたいと思います。
再度、身体症状症のポイントをまとめます。
・DSM-5で新設された概念
・身体症状が医学的に説明可能かどうか」に関係なく、患者さんに症状による過度な不安、苦痛、行動変化が起こっていないかを重要視している。
身体症状症の診断基準
次に、DSM-5における身体症状症の診断基準を見てみましょう。

確かに“医学的に説明できない”という文言はみられず、“身体症状があり、患者さんの日常生活への影響でていること”がフォーカスされていることがわかりますね。
また、身体症状症に加え、以下の2つの疾患概念をまとめ、“身体症状症関連障害”と呼称することがあります。身体症状症との違いを簡単に押さえておいてください。
・病気不安症:身体症状はないが、病気にかかっているというとらわれが強く、健康への強い不安があり、過剰な健康関連行動を示すもの
・転換性障害:明らかな神経疾患はないが、随意運動機能または感覚機能の変化が1つ以上あり、症状が日常生活に支障をきたしているもの
身体症状症を診断する上でのポイント
身体症状症は、“医学的に説明できない”ことばかりに意識を向けるのではなく、全人的に患者さんを診て円滑に診療することを目的に新設された疾患概念であることは繰り返しお話してきました。そうはいっても、身体症状症と診断をする際には、基本的には明らかな器質的疾患がないか、最低限の評価は行っておくべきです。
なお、補足しておきますと、たとえ器質的疾患があっても、症状への過剰な考え、感情、行動があれば、身体症状症と診断することは可能です。例えば、腰部脊柱管狭窄症があり、身体症状として足のしびれの訴えているケースを考えてみましょう。この際、しびれの症状が既存の腰部脊柱管狭窄症では説明がつかないレベルで強く、かつ日常生活に支障がでているようであれば、身体症状症と診断してもよいのです。ただし、この“腰部脊柱管狭窄症で説明がつかないレベルで”という点が適切に評価できていることが診断の前提となります。腰部脊柱管狭窄症そのものの評価はもちろんのこと、他のニューロパチーや脊椎腫瘍など、他疾患がないこともしっかり確認しておかなければいけません。
よって、ここでいう“明らかな器質的疾患”という用語は、“身体症状の説明が、すべてその疾患でついてしまうような粗大なもの”、という意味合いで使用しておりますので、前提として理解しておいてください。
さて、本題に戻り、明らかな器質的疾患を除外するアプローチを確認していきましょう。なんのかんのといいつつ、器質的疾患の除外には、“医学的に説明ができないポイント”をしっかり確認していくことが有効です。ここでは、意識すべき4つのポイントと、その具体例をご紹介します。身体症状の評価をしている際、ここに当てはまるものがあれば、「あれ?これって器質的疾患じゃないかも?」と考え、身体症状症の可能性も想起するとよいでしょう。
①解剖学的に説明できない:左右にまたがる病変、スキップする病変、デルマトームに一致しないしびれ
②病態生理的に説明できない:労作中ではなく労作後の呼吸困難、歩行時は気にならない関節痛、仕事中は気にならない胸痛
③時間経過が説明できない:部位が移動する、反復性、長期間にわたって非進行性、症状のはじめりと終わりが明確ではない
④一元的に説明できない:複数の部位にまたがる多彩な症状を訴える、症状が別の時系列で出現・消失をする
また、頻度が高く、身体症状症と診断する前に除外しておくべき個別の疾患も把握しておくと見落としが少なくなります。具体的な疾患群としては、以下のようなものがあります。
①悪性疾患:増悪傾向であれば要注意
②膠原病:最初は血液検査、身体所見がはっきりしないことも
③代謝・内分泌疾患:甲状腺機能、ビタミンB12、副腎不全については一度は必ず考える
④精神疾患:うつ病、パニック障害、アルコール依存症などは一度スクリーニングしておくとよい
個人的には、甲状腺機能、うつ病の評価はルーチンで行ってもよいと考えています。
ここまでの確認で、症状の説明がつく器質的疾患がないと判断でき、身体症状症の診断基準を満たす場合、はじめて身体症状症と診断することができるのです。
身体症状症の患者さんを診る際に意識すべきこと
最後に、身体症状症と診断したのち、どのように患者さんと向き合っていけばよいのか、ポイントを絞って解説していきます。
「やまいの歴史」を傾聴する
まず、一度は腰を据えて患者さんのお話を聞きましょう。問診してアセスメントするというよりも、人間観察モードで患者さんの話を聞くことに専念します。話の整理はしますが、医師自信の解釈は言わないことが重要です。可能であればゆっくり話を聴ける時間を確保するのがよいのですが、難しいようなら時間を決めて、外来を複数回に分けて話を聴くのもありです。患者さんがどのような症状でどのように苦しんできたのか、最初に理解しておきましょう。
身体症状症の多くの患者さんは、過去にきちんと話を聴いてもらった経験がありません。ここでしっかりとお話を伺うことで、患者さんとの信頼関係を構築できます。また、話してもらう中で、患者さんの気持ちの整理をつけてもらうことも目的の一つです。
症状の存在を認めつつ、身体保証を行う
必ず身体症状の存在を肯定し、これまでがんばってきた患者さんをねぎらってあげましょう。いうまでもなく、「何も病気はないんだけど」「精神的なものなんじゃない?」「気のせいだよ」というような対応はNGです。
併せて、器質的疾患を検索した結果として、“少なくとも重篤なものではない”ことを説明し、身体保証を行いましょう。ここでの注意点は、“器質的疾患を否定し過ぎない”ことです。あまり強く断定してしまうと、患者さんとの信頼関係を損ねてしまう可能性があります。後述するように、長く付き合っていくことが身体症状症の診療では重要であるため、焦りは禁物です。
“アース”しながら、長く付き合う
“アース”というのは、たまった電気を地球に逃がすことを言います。身体症状症の診療で重要なのは、“医師が患者さんのフラストレーションを地球に逃がし、アースの役割を担うこと”です。我々医師は、特性上すぐに目の前の患者さんの苦痛を取ってあげたいと思うものですが、身体症状症の診療ではその思いが裏目に出てしまいやすい傾向があります。“治そうとする”、“教え導く”、“治療する”という前のめりな姿勢だと、患者さんとぶつかってしまい、自分から離れていってしまうおそれがあります。かえって“自然に治るもの”、くらいのスタンスの方が、継続的に診療にあたることができます。他の言例え方をしますと、“お見舞い”に行くような気持ちで診療にあたるとよいでしょう。
また、身体症状症の診療では、医療従事者も陰性感情を抱きやすい傾向があるのは事実です。医師側も、アースをしてフラストレーションためないようにするのが診療のコツといえるでしょう。我々も頑張りすぎず、気長に診療を続けていくことに力点を置きましょう。
心身相関への気づきを促す
前述のようなスタンスで継続的な外来を設けつつ、折をみて“心身相関への気づき”を促します。心身相関とは“身体症状と心理状態の間に関連があること”を指します。身体症状症では、以下の図のような心身相関が起こっており、身体症状(痛みなど)に意識が向いて、どんどん悪化していく負のスパイラルに陥っています。最終的にはこのスパイラルを解消させることで、身体症状症を改善させることを目標に診療にあたります。

ただし、この“とらわれ”を解除するのは容易ではなく、信頼関係ができる前に無理に介入してしまうと患者さんが自分から離れていってしまうおそれがあります。そのため、これまでのような手順を踏み、患者さんも自分もフラストレーションのアースを行うことで、まずは持続可能な身体関係を築くことが重要なのです。
では、介入できる段階に至ったとして、どのように患者さんにアプローチをしていけばよいのでしょうか?具体的には、患者さんの中で以下の思考回路を作り上げていく必要があります。
①必ずしも「症状がある=器質的原因がある」わけではない
②心理的要因が症状悪化につながっている
③この世に魔法の薬はなく、治すのは医師ではなく自分(リハビリのようなイメージ)
「といわれても、結局どうやってこの思考回路を作り上げるんだ!?」という疑問の声が挙がるかもしれませんが、残念ながらそこはケースバイケースということになってしまいます。
以下のように患者さんにお伝えすると、比較的理解してもらいやすいかもしれません。
「意識をすればするほど、感覚は過敏になります。眉間にペンを近づけると、触れていないのに嫌な感じがしますよね。あれと同じで、症状を気にすればするほど、悪くなったように感じてしまうのです。症状があってもできることに取り組み、症状に意識を向けないようにすることで、少しずつ症状をなくしていくことを目標にしましょう。」
薬物治療は頑張りすぎない
身体症状症では、SSRIを始めとした抗うつ薬のエビデンスがありますが、万人に効果があるわけではありません。あくまで診察・対話による非薬物療法を中心に行います。
もし抗うつ薬を用いるのであれば、
・何度か診察を行い、患者さんとの信頼関係が構築できている
・身体症状がなかなか改善しない
・身体症状に伴いうつ症状、不安障害など、精神症状を合併している
といった条件を満たした患者さんに限定し、なおかつ治療薬の効果が限定的であることを説明した上で処方を行うのがよいでしょう。もちろん、効果が乏しようならダラダラと続けるべきではありません。
また、漢方薬も選択肢として検討してもようですが、抗うつ薬と同様、適応は慎重に選ぶべきです。もし処方するのであれば、東洋医学的診察できちんと証を評価し、患者さんに合った漢方薬を選択しましょう。
不定愁訴に処方されやすい薬剤として、メコバラミンやエペリゾンがありますが、これもダラダラ投与しない方がよいです。これは、「症状を治すのは薬だ」という、身体症状症の治療の上では誤った思考回路を増強してしまうためです。
それでも離れていってしまう患者さんがいることを受け入れる
上記のような対応をすることで、身体症状症の診療はかなりやりやすくなると思いますが、それでも信頼関係が構築できず、外来に来なくなってしまう患者さんもいらっしゃいます。こうなると、「うまく診療ができなかった」と落ち込んでしまう方もいらっしゃると思いますが、あまり気にし過ぎないことが重要です。
身体症状症の患者さんは神経質な方も少なくなく、こちらのちょっとした言動であったり、人間としての相性が合わないというだけでも離れていきやすいものです。また、器質的疾患の存在への執着が捨てきれず、身体症状症として対応する医師から離れ、ドクターショッピングを繰り返される方もいます。
このように、我々医師個人の能力ではどうすることもできない患者さんも多いため、最低限の振り返りはすれど、過度に引きずりすぎない方が精神衛生上も好ましいのです。
参考
1)かかりつけ医でもできる!心療内科的診療術 大武陽一 金芳堂
2)UpToDate
3)DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引き 医学書院