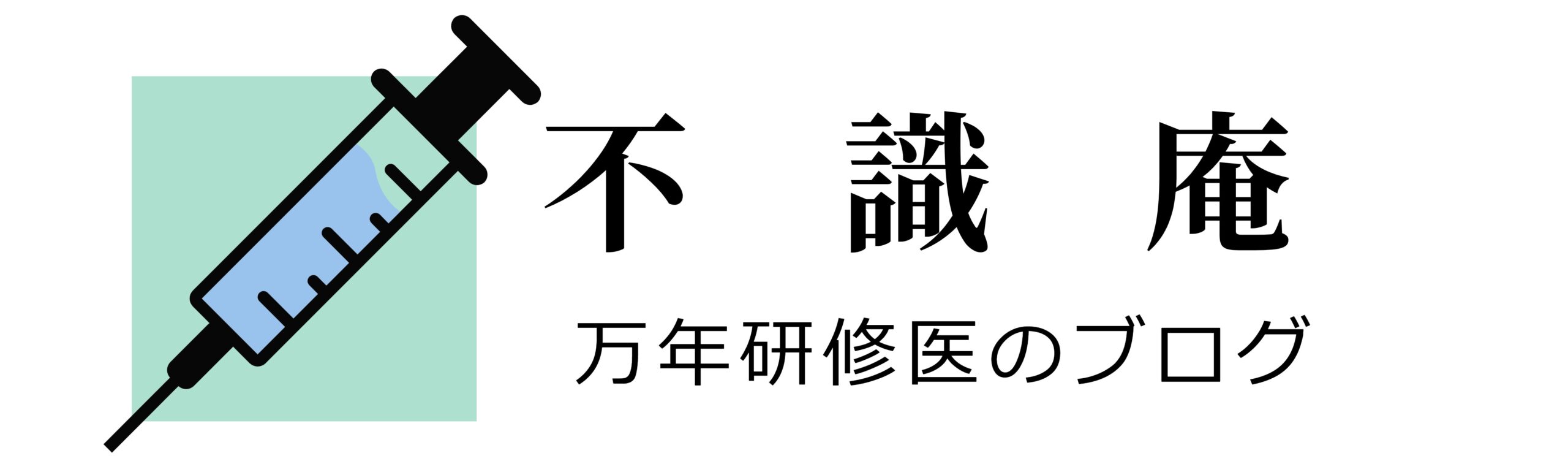勤務先の異動等でバタバタしており、ほとんどブログの更新ができておりませんでした。ようやく落ち着いてきたため、更新を再開していきたいと思います。
さて、今回は『血管内リンパ腫』に関するまとめ記事です。新しい病院に赴任して早速、この疾患の症例に関わることになりました。血管内リンパ腫といえば鑑別診断系のカンファでよく話題に挙がりますが、頻度が低く極めて珍しい疾患であるため、私も実際に診療するのは今回が初めてでした。
血管内リンパ腫とは
血管内リンパ腫(intravascular lymphoma:IVL)は、全身の細小血管内に腫瘍性B細胞が選択的に増殖する、極めて稀な節外性B細胞リンパ腫です。IVLと略されることが多いのですが、正式には血管内大細胞型B細胞リンパ腫(intravascular large B-cell lymphoma:IVLBCL)と呼称されます。
リンパ節腫脹を欠き、発熱や倦怠感など非特異的な症状で発症するため、診断が非常に難しい疾患として知られています。
1980年代には剖検で初めて診断されることが多かったものの、近年は疾患認知の広まりと生検技術の進歩により、生前診断例が増加しています。腫瘍細胞は主として毛細血管や後毛細静脈内に充満し、周囲組織への浸潤がほとんどみられません。そのため臨床的には腫瘤形成を伴わず、画像上も異常を見つけにくいという特徴があります。
疫学
IVLBCLは非常に稀な疾患であり、正確な有病率は不明です。昨今は知名度が上昇し、診断方法も確立しているため、診断される機会が増えてきています。
発症年齢の中央値は60〜70歳代、男女差はありません。
地理的には、欧米では中枢神経・皮膚病変を主体とする「古典型」が多く、アジアでは血球貪食症候群を合併する「血球貪食型」が多い傾向があります。また皮膚病変のみを呈する「皮膚限局型」も知られており、比較的予後良好とされます。
病態
生物学的には、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の一亜型に位置づけられます。
多くは非胚中心B細胞型(non-GCB型)であり、分子生物学的にもDLBCLの活性化B細胞型(ABC型)に類似しています。
遺伝子解析では以下の変異が高頻度に認められます:
・MYD88変異(約50〜60%)
・CD79B変異(約60〜70%)
・SETD1B変異、CDKN2A/2B欠失
・PD-L1/PD-L2構造異常(約30〜40%)
これらは免疫逃避機構やB細胞受容体経路の活性化と関連し、IVLBCLの病態形成に関与すると考えられています。
また、腫瘍細胞はCD29(β1 integrin)などの血管外遊走に関与する分子の発現が低下しており、血管内にとどまる特性をもつ、ないしは血管内皮や類洞内皮をニッチとして増殖することが示唆されています。

症状
IVLBCLの症状は多彩で、しばしば「臓器障害を伴う不明熱・不明炎症」として発症します。
代表的な症候は以下の通りです。
・発熱
・全身倦怠感、体重減少(B症状)
・中枢神経症状:認知機能低下、麻痺、けいれん、脳梗塞様発作
・皮膚症状:紅斑、紫斑、硬結、結節など
・呼吸器症状:労作時呼吸困難、スリガラス影
・血液異常:貧血、血小板減少、LDH上昇
・血球貪食症候群(HPS)合併例では肝脾腫・汎血球減少を伴う
欧米でよくみられる「古典型」は中枢神経症状(39~76%)、皮膚症状(17~39%)の頻度が高く、典型的には発熱、皮膚病変、急速に進行する神経学的徴候(認知症、脳卒中様症状、末梢神経障害)といった経過をとります。
一方、日本を含めたアジアでは「血球貪食型」が多く、「古典型」と比較して中枢神経症状(27%)、皮膚病変(15%)は少ないものの、骨髄、脾臓、肝臓の病変を呈し、血球貪食症候群を併発するリスクが高いと言われています。血球貪食症候群は致命的な転帰を辿ることが多く、「古典型」と比べて予後は不良です。また、「皮膚限局型」では病変が皮膚にとどまり、若年女性に多く、予後良好とされます。
検査所見
血液検査でよく認める所見は以下の通りです。

LDH上昇はほぼ全例で認めます。よって、不明熱、不明炎症にLDH上昇を伴うような場合は、本疾患を必ず想起すべきです。また、本邦では血球貪食症候群を伴うことが多いため、貧血、汎血球減少といった所見にも注目するとよいでしょう。
画像では、以下のような所見がみられます。

リンパ節腫大や明らかな腫瘤形成をきたすことは稀ですが、肝脾腫、腎・副腎腫大を認めることがあります。また、腫瘍細胞が肺血管に浸潤するとCTで肺病変を、脳血管に浸潤すると頭部MRIで虚血性変化を認めます。FDG-PETでは骨髄や肺、肝、脾に集積を認めることが多く、集積部位を狙って生検を行うと診断に有用です。
診断
IVLは特徴的な臨床像を欠く上、ランダム皮膚生検などの組織診断が唯一の確定法となるため、まずは疑うことが重要です。特に以下のような臨床経過の場合は本疾患を想起する必要があります。
・LDH高値を伴う不明熱、不明炎症
・発熱+神経症状+皮疹
・原因不明の血球減少や肝脾腫
・血球貪食症候群を疑う症例
診断には、ランダム皮膚生検+骨髄生検の併用が有用です。
ランダム皮膚生検とは、その名の通り皮膚を何か所かランダムに生検する手法です。ランダムといっても、皮疹があるのであれば、その部位の生検を行います。皮疹がない場合も、老人性血管腫のある場所を狙って生検すると、診断精度が高まります。一般的に、パンチ生検よりも切開生検の方が好ましく、血管の豊富な皮下脂肪織を含めての採取が推奨されています。
「血球貪食型」では骨髄浸潤の頻度が高いため、骨髄生検も有用です(血球貪食症候群を疑う場合、骨髄生検は自ずと行うことになるはずですが)。
ランダム皮膚生検+骨髄生検で診断がつかなかった場合、他の部位の生検を検討します。この場合、CTやPET-CTで異常のある臓器を狙うと診断に繋がる可能性が高くなります。
鑑別疾患としては、IVL以外のリンパ腫に加え、血管が病変の首座となる疾患が重要です。具体的には、ANCA関連血管炎、感染性心内膜炎、SLEなどが挙げられます。また、血球貪食症候群を来す疾患として成人Still病も鑑別となります。不明炎症+肝脾腫という病像により、粟粒結核との鑑別が必要となることもあります。
治療
治療はびまん性大細胞性B細胞リンパ腫に準じ、R-CHOP療法(リツキシマブ+シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン)が行われることが多いです。
また、中枢神経病変を認める場合、R-CHOP療法のみでは不十分であるため、髄腔内化学療法、高容量メトトレキサート、放射線療法などを併用することもあります。
まとめ
以上、IVLについて概説してきました。最後に重要ポイントをまとめます。
・IVLは血管内でのみ増殖する稀なB細胞リンパ腫で、診断が非常に難しい。
・発熱+LDH高値±皮疹・神経症状、血球貪食症候群で本症を疑う。
・皮膚生検+骨髄生検が診断の鍵。
・治療はR-CHOP±中枢神経治療。
参考
1)UpToDate:Intravascular large B cell lymphoma
2)日内会誌 110:1434~1440,2021
3)Blood (2018) 132 (15): 1561–1567.