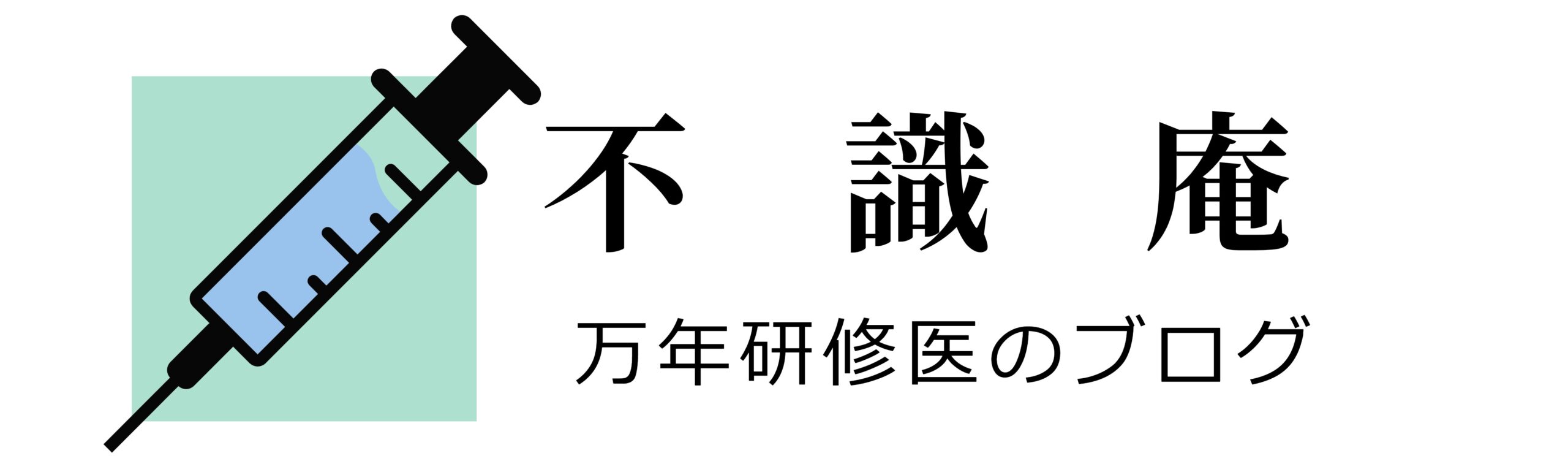イメグリミンについて
イメグリミンとは、2021年9月にリリースされた新しい経口血糖降下薬であり、ツイミーグ®という商品名で販売されています。適応疾患は2型糖尿病であり、他の多くの経口血糖降下薬と同様に、1型糖尿病に対しては適応外となっています。500mgの錠剤があり、「1回1,000mgを1日2回、朝・夕に経口投与する」という用法をとります。2025年2月9日時点での薬価は500mgの錠剤が34.1円/錠となっており、添付文書通りに使用すると、ひと月ごとの薬価は約4,000円前後になります。また、イメグリミンは腎排泄であり、現時点ではeGFR<40mL/min/1.73m2の場合、投与が推奨されていません。
イメグリミンはメトホルミンに類似した化学構造を持っており、以下の図ようにメトホルミンが閉じて環状になったような構造をしています。

イメグリミンは「乳酸アシドーシスリスクのないメトホルミン」をコンセプトに開発されており、実際にイヌやマウスレベルでの研究では、イメグリミンの血清乳酸値上昇効果はメトホルミンに比して低いことが示されています1)。
しかし、血糖降下作用の機序については両者の間で差異があるようです。メトホルミンはミトコンドリアに作用することで肝臓での糖新生を抑制し、血糖降下作用を示します。一方、イメグリミンはメトホルミンと比較するとミトコンドリアへの作用が弱いことがわかっており、糖新生抑制効果はそれほどではないと考えられています2,3)。イメグリミンの血糖降下作用はグルコース依存性インスリン分泌増強作用によるものとされており、作用機序だけみればメトホルミンというよりもむしろDPP-4阻害薬やGLP-1受容体アゴニストに類似しているといえます。
イメグリミンのエビデンス
では、ここからはイメグリミンのエビデンスについて、3つの国内第3相試験を中心に確認していきましょう。
TIMES1試験
TIMES1試験はイメグリミン単独療法の有効性・安全性を評価した試験です4)。日本人2型糖尿病患者でHbA1c 7.0-10.0%の213人を対象とし、イメグリミン群(1,000mgを1日2回)に106人、プラセボ群(プラセボを1日2回)に107人を無作為に割り付けました。試験デザインは無作為化二重盲検並行群間プラセボ対照試験であり、投与から24週後のHbA1cのベースラインからの変化を主要評価項目としています。
結果として、イメグリミン群ではHbA1cが0.72%低下し、プラセボ群では0.15%上昇しました。その結果、群間の差は-0.87%(95% CI -1.04 to -0.69, P<0.0001)となり、イメグリミンの有意な血糖降下効果が示されました。また、副次評価項目として、24週後にHbA1c < 7.0%を達成した割合は、イメグリミン群で35.8%、プラセボ群で7.5%(P<0.0001)であり、HbA1cが7%以上低下した割合もそれぞれ57.5%、11.3%(P<0.0001)と、いずれもイメグリミン群で有意に高い結果でした。
安全性については、イメグリミン群で44.3%、プラセボ群で44.9%の患者が何らかの有害事象を報告しましたが、大部分は軽度であり、重篤な有害事象の発生率に大きな差はありませんでした。低血糖の発生率はイメグリミン群で2.8%、プラセボ群で0.9%でしたが、重篤な低血糖は報告されませんでした。
これらの結果から、イメグリミンは日本人2型糖尿病患者においてHbA1cを有意に低下させ、かつ安全性プロファイルもプラセボと類似していることが示された、と結論付けられています。

TIMES2試験
TIMES 2試験は、日本人2型糖尿病患者を対象に、イメグリミン単独療法および既存の糖尿病治療薬との併用療法の長期安全性と有効性を評価した第3相試験です5)。本試験は52週間にわたり実施され、イメグリミンの持続的な効果と安全性を検討しました。
対象となったのは、食事療法・運動療法のみ、または単剤療法で血糖コントロールが不十分な2型糖尿病患者 714名です。そのうち、イメグリミン単独療法群には 134名、以下の薬剤と併用した群には 580名 が割り付けられました。
・α-グルコシダーゼ阻害薬併用: 64名
・ビグアナイド薬併用: 64名
・DPP-4阻害薬 併用: 63名
・グリニド薬 併用: 64名
・GLP-1受容体アゴニスト併用: 70名
・SGLT-2阻害薬併用: 63名
・スルホニル尿素薬 併用: 127名
・チアゾリジン薬併用: 65名
本試験の主要評価項目は安全性の評価でした。試験期間中、75.5% の患者が何らかの有害事象を経験しましたが、その大部分は軽度または中等度でした。重篤な有害事象は 5.6% に発生しましたが、いずれも試験薬との関連はありませんでした。また、低血糖の発生率は以下のとおりでした。
・単独療法群: 3.7%
・併用療法群: 3.1%~16.5%
・グリニド薬併用群: 14.1%
・スルホニル尿素薬併用群: 16.5%
・他の併用群では概ね 10%未満
・重篤な低血糖は報告なし
副次評価項目としてHbA1cの変化を評価しており、52週後のHbA1c変化量は以下のとおりでした。
・単独療法群: -0.46%
・併用療法群: -0.56%(SU併用)~ -0.92%(DPP4-阻害薬併用)
・GLP-1受容体アゴニスト併用群: -0.12%(効果が最小)
DPP4-阻害薬との併用 では-0.92% という最大のHbA1c低下が見られた一方、GLP-1受容体アゴニストとの併用では-0.12%と効果が最小でした。

また、52週後に HbA1c < 7.0% を達成した割合は、単独療法群で 40.3%、HbA1cが7%以上低下した患者の割合は 48.6% でした。
結論として、イメグリミンの52週間にわたる長期的な安全性と有効性が確認されました。他剤との併用も有効ではありますが、スルホニル尿素薬やグリニド薬との併用では低血糖リスクが高いこと、またGLP-1受容体アゴニストとの併用では血糖降下作用が減弱してしまうことには注意が必要です。
TIMES3試験
TIMES 3試験は、日本国内35施設で実施された 無作為化二重盲検プラセボ対照試験(16週間) と、その後の 36週間のオープンラベル延長試験(合計52週間) で構成されています6)。
対象となったのは、インスリン単独療法またはインスリン+単剤の経口糖尿病治療薬を使用しながらも血糖コントロールが不十分な 215名の2型糖尿病患者です。試験開始時のHbA1cは 7.5~11.0%、インスリン総投与量は 8~40 IU/日 で、12週間以上安定した治療を継続している患者が選ばれ、イメグリミン群には108名、プラセボ群には107名が割り付けられました。
本試験の主要評価項目は 16週後のHbA1cの変化でした。結果は以下の通りです。
・イメグリミン群: -0.63%(95% CI -0.78 to -0.49)
・プラセボ群: -0.03%(95% CI -0.18 to 0.12)
・群間差: -0.60%(95% CI -0.80 to -0.40, P < 0.0001)
イメグリミンを追加した群では、16週後にHbA1cが有意に低下しました。
副次評価項目とその結果は以下の通りです。
・HbA1c < 7.0%を達成した患者の割合(16週後)
イメグリミン群: 7.4%
プラセボ群: 0.9%(P = 0.045)
・HbA1cが7%以上低下した患者の割合
イメグリミン群: 54.6%
プラセボ群: 20.8%(P < 0.0001)
・空腹時血糖(FPG)の変化
イメグリミン群: -0.63 mmol/L
プラセボ群: -0.15 mmol/L
群間差: -0.48 mmol/L(P = 0.0522)
・低血糖の発生率
イメグリミン群: 21.3%
プラセボ群: 15.9%
いずれも 軽度の低血糖 であり、重篤な低血糖は発生せず
・52週間後のHbA1cの変化
イメグリミン群: -0.64%(95% CI -0.82 to -0.46)

結論として、インスリン単独療法で血糖コントロールが不十分な日本人2型糖尿病患者において、イメグリミンの追加によりHbA1cが有意に低下することが確認されました。さらに、この効果は52週間持続 し、インスリン投与量を増加させることなく血糖コントロールが改善されました。
イメグリミンに対する現時点のスタンス
以上、TIME1~3試験についてまとめてきました。これらを踏まえ、私としては「イメグリミンは現時点ではメトホルミン以上に有効性・安全性が確立しているとは言い難いため、基本的には使用せず、さらなるエビデンスの集積を待つ」というスタンスを取りたいと思います。
イメグリミンは開発のコンセプトだけをみるとメトホルミンの上位互換のような印象を受けますが、そもそもメトホルミンの乳酸アシドーシスは非常に頻度が低いため、TIMES1~3試験のサンプルサイズでは「イメグリミンでは本当に乳酸アシドーシスが起こらないのか?」という点は判断が困難です。また、メトホルミンが有する脳・心血管疾患抑制効果がイメグリミンに存在するのか、という点も明らかになっていません。今の時点では、イメグリミンには「血糖降下作用がある」、「短期間・少人数の使用では大きな有害事象が起こらなかった」ということ以上のエビデンスは示されていないといってもよく、積極的に使用する段階にないと考えます。
今後の展望ですが、
・脳・心血管疾患を抑制する効果がある
・リアルワールドにおいてもメトホルミンと比較して乳酸アシドーシスのリスクが少ない
・高齢者にも安全に使用できる
といったことが示されれば、イメグリミンの地位も上昇してくる可能性があります。
これまでの記事でも繰り返しお伝えしている通り、2型糖尿病の治療では、「脳・心血管疾患予防効果のあるメトホルミン、SGLT-2阻害薬、GLP-1受容体アゴニストを優先的に使用し、次の選択肢として高齢者にも投与しやすいDPP-4阻害薬を検討する」という方針を基本にすれば、大きな方向性としては問題ないかと思います。
参考
1)Physiol Rep. 2022 Mar;10(5):e15151.
2)Endocrinol Diabetes Metab. 2021 Feb 23;4(2):e00211.
3)Sci Rep. 2023 Jan 13;13(1):746.
4)Diabetes Care. 2021 Apr;44(4):952-959.
5)Diabetes Obes Metab. 2022 Apr;24(4):609-619.
6)Diabetes Obes Metab. 2022 May;24(5):838-848.
7)内科学会雑誌 2023 年 112 巻 9 号 p. 1607-1612