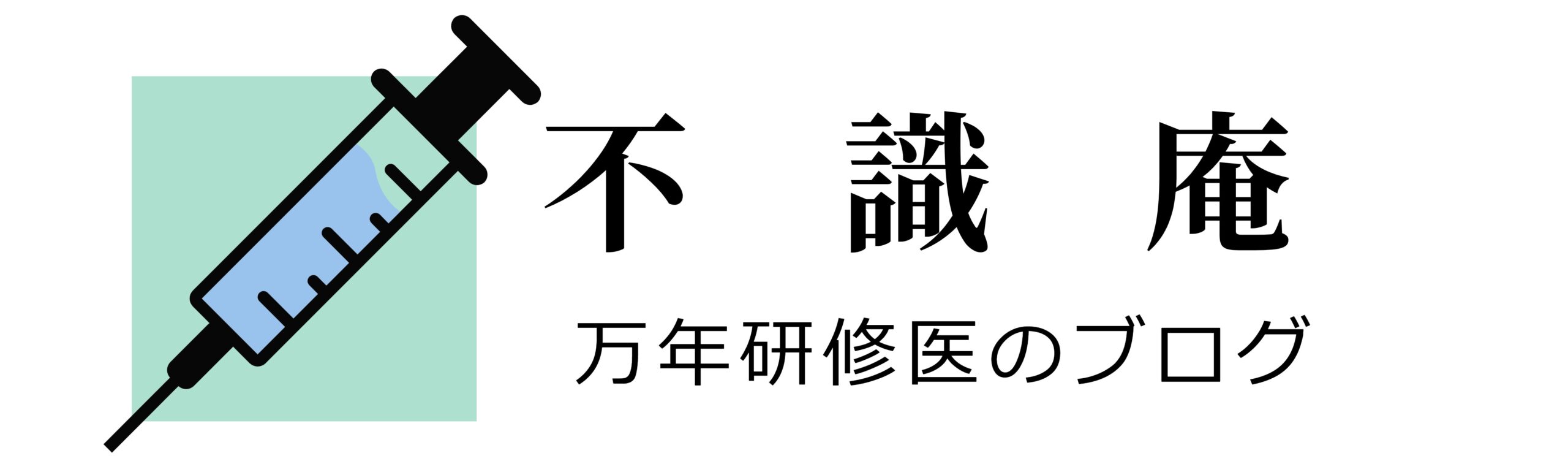手根管症候群とは
解剖
正中神経は外側神経束の内側枝と内側神経束の外側枝が腋窩動脈の前面で合し、正中神経となります。「上腕内側→肘窩→(前骨間神経を分枝として出す)→前腕→(掌枝をだす)→手根管→手」を走行します(下図参照)。正中神経の掌枝は手根管に入る前に分枝し、手掌母指球周囲の感覚を担います。

病態
手根管とは、手根骨と横手靭帯とからなるトンネルであり、9本の指屈筋腱と一緒に正中神経が走行しています。この部分で正中神経が圧迫され種々の症状がでるものを手根管症候群と呼称します。
多くは特発性で、先天性に手根管の狭小があり、手関節の屈曲や母指と他の指で何かをつまむような動作で手根管内の圧が上がり、正中神経が靭帯に圧迫され発症すると考えられています。
発症因子としては屈筋腱の腱鞘炎、滑膜炎、アミロイド沈着、腫瘍、ガングリオンなどによる内腔の狭小化をきたすもの、糖尿病性ニューロパチーなどによる神経側の脆弱性、妊娠・甲状腺機能低下症などによる浮腫性の要因などが知られています。
女性は男性に比較し3-10倍罹患しやすいとされ、上肢のしびれを主訴に来院する患者の40%が手根管症候群であったとの報告もあります。

臨床症状
典型的にはRing finger splitと呼ばれるように、環指の撓側から母指にかけて、手掌側主体にしびれを自覚します。母指球は手根管以前で分岐する正中神経の掌枝が支配するため、スペアされることが多いです。ただし、「自覚的」な症状は正中神経支配領域を超えることがあり、患者によっては前腕や上腕にかけてのしびれを訴えることもあります。
通常は感覚障害が主体で、運動障害は目立たないことが多いですが、進行すると短母指外転筋、母指対立筋、虫様筋の障害が起こります。
特徴的な病歴として、
・痛みで夜間や早朝に眼が覚める
・車や自転車の運転、料理、裁縫など、手を使う動作で増悪する
・手を振ると改善する(flick sign)
があり、患者さんに確認するようにしましょう。

診断
診断基準
手根管症候群に絶対的な診断基準はありませんが、下記のWittらの提唱する診断基準が参考になります。ここでのポイントは、Major criteriaが病歴のみで構成されている点です。しっかり患者さんから手根管症候群らしい病歴をとりに行くようにしましょう。

身体所見
前述の通り、「自覚的」なしびれは正中神経の支配領域を超えることがありますが、「他覚的」な感覚障害はring finger split、母指球のスペアを認めます。「他覚的所見はうそをつかない」ことを押さえておきましょう。
誘発法としてはTinel徴候とPhalen徴候が有名ですが、感度は高くない点に注意しましょう。
Tinel徴候:手根管部をたたくことで正中神経支配域に沿った異常感覚を誘発することができれば陽性とする。
Phalen徴候:手関節を屈曲位で1分間合わせて異常感覚が増悪すれば陽性とする(手根管内圧が上昇することで正中神経圧迫が強くなるため)。
また、進行すると短母指外転筋など母指球筋に萎縮を認めることもあります。
検査
神経伝導検査が確定診断に有用です。SCSでの手掌-手首間のSCV低下やMCSでの遠位潜時延長などが手根管症候群を示唆する所見です。病歴や身体所見のみでは手根管症候群の確診が難しい場合には一度専門機関の紹介を検討しましょう。
治療
まずは局所の「安静」を指示する必要があります。
保存療法として有効性が示されているのはステロイドの局所注入ですが、非専門医で行えるかは個々のスキルに依存します。経口ビタミン剤や鎮痛薬についてはエビデンスレベルの高い研究が不足しているのが現状です。
ステロイド内服も有効とされており、短期使用(PSL 20-25mg 7日程度)を試してみるのも選択肢です。ただし、あくまで「短期」の使用に留めましょう。
保存加療で改善を認めない場合、手根管開放術が選択肢となります。症状が持続しQOLが障害されるような症例では早期に専門機関への紹介を検討しましょう。
参考
・Up to date
・非専門医が診るしびれ 塩尻俊明 羊土社
・標準的神経治療 しびれ感 日本神経治療学会
・医学事始
正中神経 median nerve