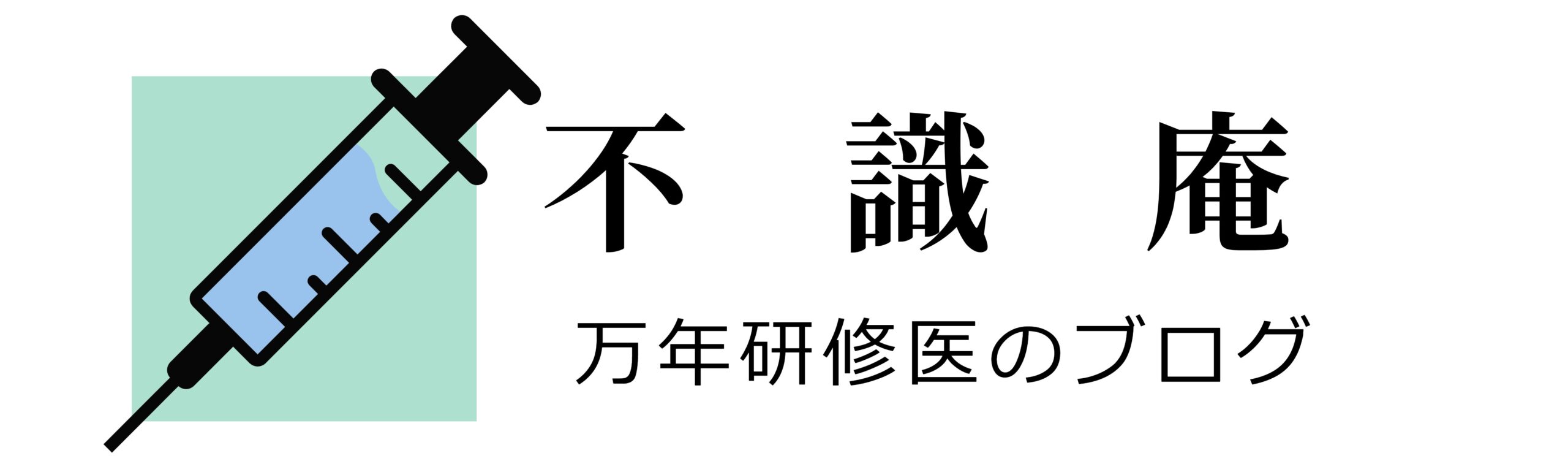はじめに
肺胞低換気、拡散障害、シャント、換気‐血流比(V/Q)不均等、…。皆さんも医学生時代、生理学の授業で“呼吸不全の4要素”として一度は学んだはずです。ただ、こういった基礎医学の知識は臨床に出ると意外と忘れ去られてしまい、実際の診療ではあまり活かされていないのが実情ではないでしょうか。かく言う私も、これまではぼんやりとした知識で、きちんと使いこなせてはいませんでした。
しかし、この4要素を理解しておくことは、呼吸不全の患者さんを診療するうえで非常に重要です。そこで今回は基本に立ち返り、“呼吸不全の4要素”について整理してみたいと思います。
酸素輸送の全体像:大気から組織まで
呼吸不全を理解する第一歩は、酸素が「大気 → 肺胞 → 血液 → 組織」と運ばれる流れを把握することです。ここを押さえておくと、“呼吸不全の4要素”の理解がぐっと容易になります。

①大気→肺胞(肺胞換気)
呼吸運動により、外気が気道を通って肺胞に到達する過程です。
・規定因子:分時換気量です。分時換気量は、気道抵抗・肺コンプライアンス(肺の膨らみやすさ)・呼吸筋力によって変動します。
・このプロセスが障害されると、肺胞低換気が生じます。
②肺胞→肺毛細血管(拡散)
肺胞内の酸素分圧(PAO₂)と毛細血管血液の酸素分圧(PaO₂)の勾配に従い、酸素が肺胞膜を通過するプロセスです。
・規定因子:酸素分圧差、拡散面積、肺胞膜の厚さ
・この部分が障害される状態を 拡散障害 と呼びます
③血液→組織(酸素運搬と利用)
酸素は主にヘモグロビンに結合して運ばれ、末梢で酸素解離曲線に従い組織に供給されます。
・規定因子:Hb濃度、心拍出量、酸素解離曲線。
・このプロセスは 貧血、心不全を含めた循環不全、一酸化炭素中毒、ミトコンドリア障害で障害されますが、呼吸不全の範疇には含まれないため、本稿では詳細を割愛します。
④換気血流比とシャント
肺全体として 換気(V)と血流(Q)のバランス が取れてはじめて効率的なガス交換が成立します。
・V/Q高値:換気はあるが血流が乏しい/ない → 酸素化に直接寄与しない。
・V/Q低値:換気が相対的に不足 → 酸素化が不良(酸素投与で改善しやすい)。
・V/Q=0(シャント):換気がなく血流のみが通る → 酸素投与への反応が乏しい。

ここまでが酸素輸送の全体像です。次に、“呼吸不全の4要素”を一つひとつ見ていきましょう。
肺胞低換気
肺胞気と血中の分圧差によって、酸素は肺胞から血中へ、二酸化炭素は血中から肺胞へと拡散します。本来であれば、肺胞気は呼吸により絶えず入れ替わっているため、PAO₂は約100mmHg、PACO₂は約40mmHgに保たれます。
ところが“肺胞低換気”では換気量が低下することで肺胞気の入れ替わりが不十分となり、PAO₂が低下し、PCAO₂が上昇します。その結果、PaO₂低下(低酸素血症)とPaCO₂上昇(高二酸化炭素血症)が生じます。

原因となるのは、COPD、神経筋疾患、薬物中毒(例:ベンゾジアゼピン)、呼吸筋疲労 などです。
酸素投与でPaO₂は改善しますが、PaCO₂の是正には不十分です。NPPVや挿管・人工呼吸 による換気補助が必要です。慢性高CO₂血症の患者では、呼吸ドライブが低酸素血症のみに依存しています。ここに酸素投与で低酸素血症を是正してしまうと、換気ドライブがなくなり、CO₂ナルコーシスを誘発してしまいます。よって、このような患者さんでは無計画な高流量・高濃度酸素投与は避け、目標SpO₂を設定して慎重に補正します。
拡散障害
正常肺では、肺胞‐毛細血管関門の面積はおよそ 50〜100 m²、厚さは多くの部位でわずか 0.3 μm 程度。安静時なら血液が毛細血管を 約0.75秒 で通過する間に酸素化は十分完了します。運動時には通過時間が 約0.25秒 に短縮しても、正常肺であればPaO₂は低下しません。
拡散障害 は、この関門が肥厚するなどして酸素の拡散に時間を要する病態で、間質性肺炎 が代表例です。

低酸素血症は安静時に目立たず、労作時低酸素血症 が顕在化しやすいという特徴があります。
酸素投与でPAO₂を上げると拡散が促進されるため、低酸素血症は速やかに改善します。また、CO₂はO₂より拡散しやすいため、通常は PaCO₂上昇は目立ちません。
シャント
“シャント”とは、肺胞での換気を経ずに動脈系へ流入する血流を指します。正常でも気管支動脈や冠静脈の一部がシャントに含まれますが、その割合は少なくPaO₂低下の原因にはなりません。
一方で 肺動静脈奇形、心房・心室中隔欠損の右→左シャント などでは、静脈血が大量に動脈へ混入し、著明な低酸素血症を引き起こします。

シャントでは、酸素投与への反応が乏しいことが特徴であり、100%酸素でもPaO₂が期待通り上がらない場合には疑う必要があります。
また、シャント血にもCO₂は多いものの、換気ドライブの亢進によりPaCO₂は保たれる(むしろ低下し得る) ため、通常は著明な高CO₂血症は目立ちません(ただし、重症例を除く)。
換気-血流比(V/Q)不均等
最後に V/Q不均等 です。これは低酸素血症の原因の中で最も頻度が高く、かつ理解が難しい概念です。
まず、シンプルなモデルで考えてみましょう。肺胞が3つあり、それぞれV/Qが低値(換気不足)、正常、高値(血流不足)だとします。各肺胞から出てくる血液の酸素含量はそれぞれ16mL、19.5mL、20mL/100mL血液とします。これらが混合すると、全体の酸素含量は17.9mL/100mLとなります。つまり V/Qの低い領域が血液全体を引き下げる ため、低酸素血症が生じるわけです。一方、V/Q高値の領域は酸素含量がやや多いものの、それ以上酸素を増やせないため、低値領域の影響を打ち消すことはできません。

疾患とV/Q不均等
実際の疾患を念頭に、V/Q不均等について考えてみましょう。
まずは V/Qが低下する場合 です。典型的な疾患としては肺炎、うっ血性心不全、無気肺などが挙げられます。これらの病態では、肺胞内に液体が貯留したり、肺胞自体が虚脱したりすることで換気(V)が著しく低下します。その結果、V/Qの低い領域が増加し、十分に酸素化されない血液が体循環へ流入するため、低酸素血症が生じるのです。なお、換気(V)が極端に低下し0となった場合、シャントと同様の病態となります。

次に、V/Qが高値となる場合 を考えます。代表疾患は肺塞栓症です。肺動脈が閉塞すると、その領域の血流(Q)は極端に低下し、局所的にV/Q比は高値を示します。しかし、ここで重要なのは前述した通り、「V/Q高値の領域が増えるだけでは低酸素血症は生じない」という点です。それにもかかわらず、肺塞栓が呼吸不全の代表的疾患である理由は、肺全体をマクロに眺めると理解できます。すなわち、塞栓によって血流が途絶した分の血液は、残存する正常肺へと再配分されます。その結果、これらの領域では血流(Q)が相対的に過剰となり、V/Qが低下してしまうのです。こうして新たに“V/Q低値領域”が生じることによって、低酸素血症が顕在化します。さらに臨床的には、塞栓部位の炎症に伴って肺炎や無気肺が併発したり、右心負荷の増大によって卵円孔開存などの右左シャントが顕在化したりと、複数の要因が組み合わさって低酸素血症を悪化させることも少なくありません。

このように考えると、V/Q不均等は単一疾患に特有の病態というより、低酸素血症をきたす多くの疾患に共通する基盤であることがわかります。実際、COPDや間質性肺炎といった「肺胞低換気」「拡散障害」として理解されがちな疾患でも、V/Q不均等の要素が少なからず含まれています。語弊を恐れずに言えば、低酸素血症を呈する病態の背景には必ずV/Q不均等が存在すると言っても過言ではなく、4要素の中でも最も臨床的に重要な概念だといえるのです。
また、V/Q不均等では肺胞気の酸素分圧を上昇させることで血液中の酸素含量を増加させられるため、酸素投与に対する反応性は良好です。
一方で、二酸化炭素に関しては換気ドライブが亢進することで排出が維持されるため、通常は高CO₂血症を呈しません。
実臨床でどのように活用できるのか?
ここまで低酸素血症の4病態についてみてきました。ここでそれぞれの病態について、表にまとめておきます。
さて、ここからはこの低酸素血症の4病態を、どう実臨床に活かすのか?という点を深堀りしていきたいと思います。私の独断と偏見ではありますが、①病態の把握・診断に活かす、②治療方針の決定に活かすの2点が重要になると考えています。
病態の把握・診断に活かす
低酸素血症の患者さんを前にしたとき、まず大事なのは「低酸素血症の原因がどこにあるのか?」を整理することです。単に「低酸素血症だから酸素を投与する」のではなく、4病態のうちどれが優位なのかを意識することで、診断の精度はぐっと高まります。
具体的なアプローチは以下の通りです。
①PaCO₂の変化を見る:高CO₂血症なら肺胞低換気をまず疑う。
②酸素投与への反応を見る:改善すればV/Q不均等や拡散障害、改善が乏しければシャントを強く考える。
③労作時低酸素血症の有無:安静時は正常でも、運動で顕在化するなら拡散障害が典型。
ここで補足しておきたいのが、V/Q不均等とシャントの関係性です。両者は明確に線引きされるものではなく、実際には同一スペクトラム上にある概念です。換気がある程度残っていれば酸素投与で改善する「V/Q不均等」、換気が完全に失われてV=0となれば「シャント」と呼ばれる状態です。例えば肺炎では、肺胞の換気低下によってV/Q不均等が生じますが、さらに進行して無気肺となり換気が消失すれば、病態はシャントへ移行します。
加えて、呼吸不全の4病態は現実にはグラデーションをもって併存することが多い点も重要です。
・肺炎:病変部位で換気が極端に低下し「シャント」に近い病態が生じますが、周囲では「V/Q不均等」が広がり、炎症の進展とともに「拡散障害」も加わる。
・COPD増悪:気道閉塞により「V/Q不均等」が主体ですが、重症化すれば呼吸筋疲労から「肺胞低換気」も加わり、高CO₂血症が目立つ。
・間質性肺炎:慢性的に「拡散障害」が存在しますが、進行とともに肺構造が破壊され、「V/Q不均等」や「シャント」の要素が加わる。
このように、単一の病態だけで説明できる症例はむしろ少なく、複数の要素が重なって“呼吸不全”という臨床像が形成されます。大事なのは「この患者さんではどの病態が優位か」「どの要素が酸素化不良の主因か」を常に意識して評価することです。
さらに、画像所見と組み合わせることも診断精度を高めます。本稿では詳細な読影解説は行いませんが、例えば 肺実質に明らかな異常がない場合には、肺胞低換気(神経筋疾患・喘息発作など)、シャント(肺動静脈瘻・先天性心疾患)、肺塞栓 などを考える──こうしたクリニカルパールは覚えておいて損はありません。
最終的な目標は、低酸素血症の病態を言語化する習慣を持つことです。
例えば、
・「細菌性肺炎があって、病変部位のVが低下しV/Q不均等になっているな。拡散障害も伴っていそうだ。」
・「喘息発作でVが下がり、肺胞低換気とV/Q不均等が起きて低酸素血症、高CO₂血症になっているな。」
といったように、症例ごとに肺で何が起きているのかを言葉にできるようになると、診断の精度は格段に高まります。
治療方針の決定に活かす
診断の見通しが立てば、次は治療です。呼吸不全の4病態は、そのまま治療方針の選択に直結します。
・肺胞低換気:酸素投与は低酸素血症を改善しますが、高CO₂血症の是正には効果がありません。NPPVや人工呼吸による換気補助が必要です。
・拡散障害:酸素投与で肺胞気の酸素分圧を上げれば改善が得られるため有効です。
・シャント:酸素投与への反応が乏しいのが特徴です。PEEPをかけて虚脱肺胞を再開通させる、体位管理を行う、あるいは根本的な病態(動静脈瘻、先天性心疾患)に対処する必要があります。
・V/Q不均等:酸素投与にはよく反応します。ただし、背景となる病態によって対応が異なるため、具体的に「何がV/Q不均等を引き起こしているか」を言語化しておくことが重要です。
例:肺塞栓がある → 血栓溶解や抗凝固で血流を是正
例:無気肺がある → 体位ドレナージ/PEEP上昇
最後に、低酸素血症を最もよく診療する場であろう救急外来での動きをまとめてみると、以下の3ステップになります。
①まず肺胞低換気の有無を評価し、換気補助の必要性を判断
②酸素投与を行いつつ、酸素投与への反応性、病歴、身体所見、検査所見を組み合わせて病態把握/診断を進める
③原疾患と低酸素血症の各病態に応じた治療方針を決定する
この流れを意識することで、救急外来でも病棟でも、低酸素血症へのアプローチがより論理的かつ実践的なものになるはずです。
終わりに
呼吸不全の4病態は、単なる教科書知識ではなく、臨床の現場で診断や治療の方向性を考えるうえで強力な武器になります。もちろん実際の患者さんでは複数の病態が入り混じり、単純に割り切れないことも多いですが、それでも「どの病態が優位なのか?」を意識して言語化していくことで、診療はより論理的で自信を持ったものになります。
今日からの診療で、ぜひ目の前の患者さんの低酸素血症を「4病態のどこで説明できるか?」という視点で考えてみてください。
参考
・ガイトン生理学 原著第13版 ELSEVIER
・ウエスト呼吸生理学入門 正常肺編 第2版 メディカル・サイエンス・インターナショナル
・ウエスト呼吸生理学入門 疾患肺編 第2版 メディカル・サイエンス・インターナショナル