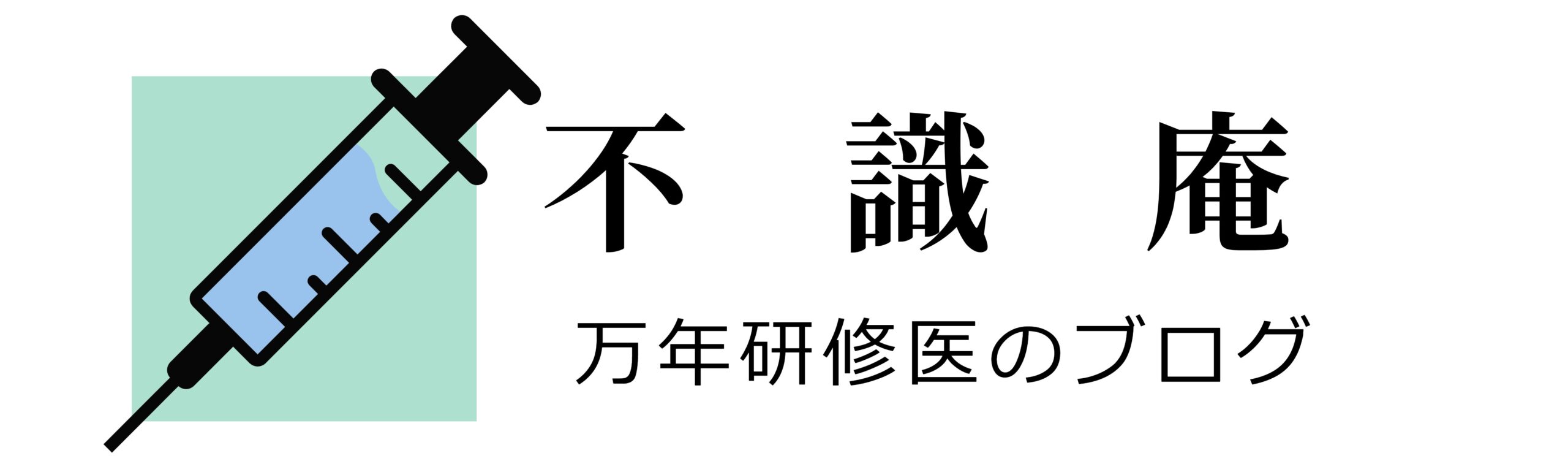2025年8月29日、高血圧の診療ガイドラインが6年ぶりに改訂されました1)。今回は改訂部分を私見を交えつつ、要点を絞って紹介していきたいと思います。
改訂ポイント①:降圧目標が変更された
最初のポイントは、以下の通り降圧目標が変更されたことです。

旧版のガイドラインでは、基本的には130/80mmHgを目標としながらも、一部の集団では140/90mmHg未満という緩めの管理が推奨されていました2)。
この“特定の集団”の中には、両側内頚動脈や主要な脳動脈の狭窄を持つ方に加え、“75歳以上の高齢者”も含まれていたため、年齢だけで目標血圧が高めに設定されるケースが多くなっていました。
一方、新版では「年齢などの背景によらず、原則130/80mmHg未満を目指す」と明確に方針が示されています。これは、高齢者に対する厳格な降圧治療が有害性よりも有益性を上回ることを示すエビデンスに基づいた変更です。
また、治療を強化すべき場面で“まあこのままでいいか”と緩い管理を続けてしまう、いわゆるクリニカル・イナーシャに対する警鐘という意味合いも含まれています。
改訂ポイント②:降圧薬のグループ分類が追加された
次のポイントは、降圧薬のグループ分類が追加されたという点です。以下にその表をお示しします。

これは、降圧薬を有効性や副作用の観点から優先度順にグループ(G)1、2、3に分類したものです。どの薬を優先して使うべきかを明確にすることで、薬剤選択の指針をわかりやすく整理することを目的としています。
まずはG1に分類された薬剤から見ていきましょう。これらは、高血圧症における脳・心血管イベントの発症抑制効果がしっかりとエビデンスで示されており、初期治療からの使用が推奨される薬剤群です。G1はさらにG1aとG1bに分けられています。G1aには「ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬」「ACE阻害薬」「ARB」の3剤が含まれ、忍容性が高く使いやすい薬剤として位置づけられています。一方、G1bには「少量のサイアザイド系利尿薬」と「β遮断薬」の2剤が該当します。これらは十分なエビデンスを持ちながらも、実臨床では使用頻度がやや低い薬剤であり、もっと積極的に使っていこうというメッセージが込められています。G1a > G1b のような印象を受けがちですが、G1aがG1bより優れているという意味ではない点には注意が必要です。
次にG2です。ここには「ARNI」と「MRA」の2剤が分類されています。脳・心血管イベント抑制の明確なエビデンスはないものの、確かな降圧効果と一定の忍容性を持つことから、G1に次ぐ位置づけとされています。
最後にG3には、「α遮断薬」や「ヒドララジン」などが含まれます。これらは起立性低血圧などの副作用が多く、忍容性が低いため、特殊な状況に限って使用が推奨される薬剤です。
改訂ポイント③:各降圧薬の積極的適応、禁忌リストが刷新された
次のポイントは、各降圧薬の積極的適応、禁忌のリストが刷新された点です。

積極的適応に関する表は旧版にもありましたが、下記の通り簡便なものでした。

これが禁忌も交えたより詳細な表に刷新されており、初学者にもより理解しやすい内容となりました。
改訂ポイント④:降圧治療のフローが追加された
最後の改訂ポイントは、降圧治療のフローが追加されたという点です。下記がそのフローになります。

先ほど紹介したグループ分類および積極的適応・禁忌を踏まえ、STEP1からSTEP3の各プロセスで、どのように薬剤を選択すればよいかがわかりやすく図解されています。旧版にもフローはありましたが、以下の通りかなり簡便な記載に留まっていました。

「結局どの薬を選べばいいのかわからない…」と悩みがちな初学者であっても、このフローに沿って考えれば大きな誤りなく治療方針を立てられるため、非常に有用な改訂ポイントだと思います。
改訂を踏まえてどうプラクティスが変わるのか?
では、今回の改訂により、実際のプラクティスにどのくらい影響があるものなのでしょうか?ここでは、改訂ポイント①、②の2つについて、私見を述べていきたいと思います(改訂ポイント③、④は初学者にとってよい改訂であり、かつ既存のプラクティスには大きな影響はなさそうなので割愛します)。
改訂ポイント①に関して
まず、降圧目標の変更について見ていきましょう。
この点は私のプラクティスにも少なからず影響があり、高齢の患者さんであっても、より積極的な降圧を目指すケースが増えていきそうです。
ただし、75歳以上の方すべてに130/80mmHgという目標を一律に適用しようとすると、多くの患者さんで内服薬の数が増えることになります。結果として、服薬アドヒアランスの低下や、過降圧に伴う副作用の増加といった有害事象が懸念されます。
したがって、新しいガイドラインの降圧目標を設定できるのは、ADLが自立していることに加え、身体機能が良好で、降圧強化による利益が有害性を上回ると考えられる患者さんに限られるべきでしょう。年齢だけで一概に区切ることはできませんが、私の場合は85歳以上であれば、従来通り140/80mmHgを目標として管理するケースが多くなると考えられます。
また、診療ガイドラインでこのように厳格な降圧目標が明示されることで、製薬企業にとって大きなメリットが生じるという視点も持っておくとよいでしょう。今回の改訂には、純粋なエビデンスだけでなく、資本主義的な要素も少なからず影響していると考えられます。したがって、そのような背景も踏まえたうえで、冷静にプラクティスへ反映していく姿勢が重要だと思います。
改訂ポイント②に関して
この部分の改訂で特筆すべきなのは、
・比較しβ遮断薬の推奨が強まったこと
・新薬であるARNIが、いきなりG2という高い地位に位置づけになったこと
の2点でしょう
まずβ遮断薬についてです。旧版では第一選択薬には含まれていませんでしたが、新版ではG1bとして事実上の第一選択薬に返り咲きました。とはいえ、β遮断薬は降圧効果の割に徐脈や倦怠感などの副作用に悩まされる印象があり、個人的には積極的適応がない限り使用しない方針です。これまで通り、基本は長時間作用型ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、ACE阻害薬/ARB、サイアザイド系利尿薬の3剤を中心に降圧療法を組み立てることになりそうです。また、この3剤を併用しても降圧目標を達成できない治療抵抗性高血圧では、MRAとβ遮断薬のいずれを追加すべきかが問題になります。この点については、臨床試験でMRAの有用性がβ遮断薬を上回ったという結果が示されており、私自身もまずはMRAを優先的に追加する方針です3,4)。
ARNIについては以下の記事でも触れている通り、降圧薬としてのエビデンスはまだ乏しいのが現状です。
また、新薬ということもあり、薬価も比較的高いという問題もあります。そのため、現時点では積極的適応がない限り、ARNIを降圧薬として使用することはないと考えています。
まとめ
最後にまとめますと、
・改訂ポイント①:降圧目標の変更はプラクティスに少なからず影響を与える。ただし、厳格な降圧目標を設定する対象は慎重に検討する必要がある。
・改訂ポイント②:降圧薬選択に関しては大きな変更はなく、これまで通り長時間作用型ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、ACE阻害薬/ARB、サイアザイド系利尿薬の3種±MRAが治療の軸となる。
ということになります。
したがって、診療ガイドラインの改訂に伴うプラクティスへの影響は、全体としては限定的といえるでしょう。
ただし、これは新版の内容が劣っているという意味ではありません。むしろ、構成や図解がよりわかりやすく整理され、初学者にとって非常に学びやすい内容に仕上がっています。個人的には、自身のプラクティスに与える影響は小さいものの、ガイドラインそのもののクオリティは確実に向上していると感じます。まだ新版を手に取っていない方は、ぜひ一度目を通してみてください。臨床での考え方を整理するうえで、きっと良い刺激になると思います。
参考
1) 高血圧管理・治療ガイドライン2025 日本高血圧学会 ライフサイエンス出版
2)高血圧治療ガイドライン2019 日本高血圧学会 ライフサイエンス出版
3)Int J Cardiol. 2017 Apr 15:233:113-117.
4)Clin Exp Hypertens. 2017;39(3):257-263.