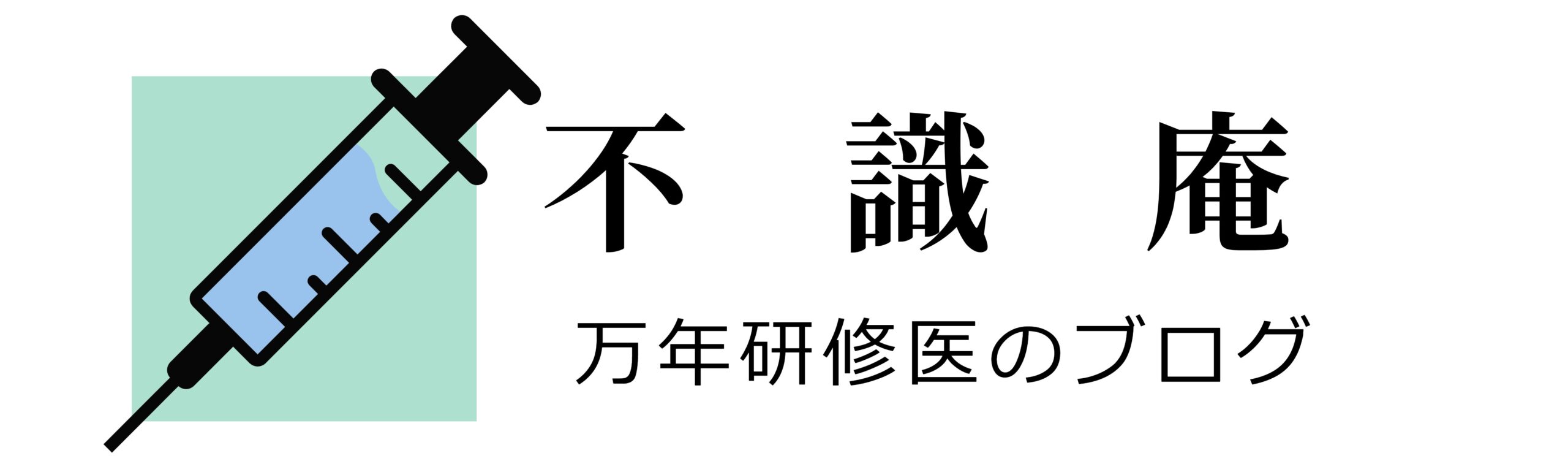カルシウムとビタミンD代謝

ざっくりカルシウムとビタミンDの代謝をまとめると上図のようになります。Caは腸管での吸収・排泄、腎での排泄、そして骨への沈着・放出のバランスにより調整されています。
腸管:1,25(OH)2D3がCa吸収を促進(PTHは1,25(OH)2D3の生成を促進し、間接的に関与)
腎臓:1,25(OH)2D3、PTHが遠位尿細管でのCa再吸収を促進
骨:PTHが骨吸収を促進
上記のような仕組みで血漿のCaイオン濃度はコントロールされています。
カルシウムとビタミンDの摂取量について
厚生労働省の食事摂取基準によれば、1日に摂取すべきカルシウム推奨量は700-800mg、ビタミンD推奨量は400-800IU/日とされています。これに対して、令和元年の国民栄養調査によると、日本人のカルシウム摂取量は平均505mg/日、ビタミンD摂取量は平均276IU/日となっており、どちらの摂取量も不足していることがわかります。骨粗鬆症でない人であっても、この2つの栄養素についてはより意識して摂取する必要がありそうです。
基本的に骨粗鬆症の治療薬についてのstudyでは、十分量のCaとビタミンDが摂取されていることが前提となって試験デザインが組まれています。臨床でも研究結果に近い効果を望むのあれば、Caの不足とvitDの不足を製剤で補ってあげた方がよい気がしますよね?今度、この疑問についてお答えしていきます。
本邦でのカルシウム製剤とビタミンD製剤
本邦で販売され、骨粗鬆症に適応がある薬剤は、それぞれ以下の通りになります。
・カルシウム製剤

・ビタミンD製剤

では、これらをどのように使い分けでいけばよいのでしょうか。
カルシウム製剤について
結論から言えばルーチンでのカルシウム製剤の投与は不要と考えます。第一の理由として、リン酸水素カルシウム、アスパラカルシウムのどちらを内服しても投与量が十分でないことが挙げられます。リン酸水素カルシウムは3g摂取すれば699mgのカルシウムが摂取できることになりますが、無機塩は腸管での吸収が悪く、生体内で利用できるカルシウムは少ないです。アスパラカルシウムは6錠内服しても133.8mg程度にしかなりません。また、第二の理由として薬剤としてのカルシウムが種々の副作用を引き起こしうるということです。一般には便秘などが多いとされますが、腎結石を引き起こしたり、心血管障害のリスクが上昇するという報告すらあります。このような観点から、カルシウム製剤は無理に投与せず、食事での摂取を推奨することがよいと考えます。
ビタミンD製剤について
日本で使用できる活性型ビタミンD3製剤には主にアルファカルシドールとエルデカルシトールの二種類があります。ビタミンD製剤は単独では骨折予防効果は証明されていませんが転倒予防効果があることが知られています。また、ビタミンD血中濃度が低いとBP製剤の効果が減弱することが報告されています。このことから、ビタミンD製剤については単独での使用は避け、BP製剤など他の骨粗鬆症薬を使用する際に限り併用を行うのがよいと考えます。アルファカルシドールとエルデカルシトールのいずれを用いてよいですが、エルデカルシトールの方が作用が強く、高Ca血症などを引き起こすリスクが高いため、筆者はアルファカルシドールを使用するようにしています。
参考
・令和元年国民健康・栄養調査報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r1-houkoku_00002.html
・南郷栄秀, 岡田悟 編: なんとなくDoしていませんか?骨粗鬆症診療マネジメント. Gノート, 4(1): 2017